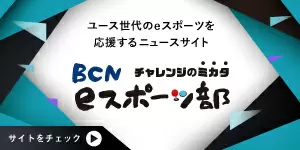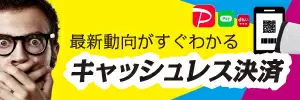2025年2月21日に東京都渋谷区の伝承ホールで、「2024年度 公推協杯 全国若手落語家選手権( https://bunp.kyodonews.jp/wakaterakugoka/2024/ )」の本選が開催された。多くの落語ファンが次世代スターの話芸を目当てに集まる中、会場で目を引いたのがオーティコン補聴器のブースだ。なぜ補聴器メーカーが落語選手権を協賛しているのか。関係者の話も交えながら、当日の様子と取り組みの詳細をレポートする。

2025年2月21日に開催された
「2024年度 公推協杯 全国若手落語家選手権」の本選のポスター
オーティコン補聴器は3回目となる24年度から本選手権を協賛しており、予選および本選会場で先進補聴器の展示や約3分で簡単に聞こえのチェックができる機器を設置したブースを出展して、聴覚ケアの啓発を行った。オーティコン補聴器の展示ブースは会場の中でも存在感があり、来場者も大いに興味を引いている様子だった。

会場受付横に置かれたオーティコン補聴器の紹介ブースでは
最新モデルの実寸大レプリカの展示と、後に続く体験型ブースへの誘導を行った
それにもかかわらず、実は日本は世界的にみて、補聴器の後進国というデータがある。欧米では難聴を自覚している人の補聴器装用率は50%を超える国もあるが、日本は15.2%(一般社団法人日本補聴器工業会「JapanTrak 2022 調査報告」)にとどまっている。
理由の一つとして挙げられるのは、補聴器に対するネガティブなイメージだ。日本では「補聴器は高齢者がするもの」という先入観が強く、本来対象となる人が装用に消極的になっている。オーティコン補聴器をフラッグシップブランドとして、展開するデマント・ジャパンではこうした状況を少しでも打破するために、昨年からBeyond15(装用率15%を超えて)というビジョンのもとに、さまざまな場所で聴覚ケアの啓発を行っている。
デマント・ジャパンの社長であり、オーティコン補聴器のプレジデントでもある、齋藤徹氏は「補聴器に対するネガティブなイメージを変えていき、もっと気軽に使ってもらえるようにしたい。適切な聴覚ケアによって、年齢を重ねても、やりたいことをあきらめず、その方らしく人生を楽しむアクティブシニアをサポートしたい」と語る。
また、「今回の協賛についても『落語が好きな皆様にいつまでも大好きな落語を楽しんでほしい、聞こえづらさを感じたら適切な聴覚ケアを行い、落語を楽しみ続けてほしい』という思いからだ」という。さらに、「情報保障の観点から、当社の補聴援助システム『エデュマイク』を会場に設置した。会場のマイク音声を互換性のある補聴器に直接とばすことができるため、補聴器ユーザーは楽に音声を聞くことができる、ユーザーの反応が楽しみだ」とも語った。

デマント・ジャパンの社長でオーティコン補聴器の
プレジデントでもある齋藤徹氏

全国若手落語家選手権を
主催する共同通信社の道下一郎氏
落語ファンにいつまでも長く落語を楽しんでほしい。そんな思いを持っていたところに、オーティコン補聴器との接点があり、お声がけをした。共同通信社とオーティコン補聴器の目指す方向が合致し、とてもいいコラボレーションにつながったという。
あまり一般に知られていないが、現在の補聴器は先進テクノロジーによって大きく進化している。例えば昨年6月に発売された「Oticon Intent(オーティコン インテント)」は、無意識に行う頭や体の動き、会話活動、周囲の音響環境の四つの側面を感知するじぶんセンサー(4Dセンサー)を搭載。装用者の最も聞きたい音を自然な音のバランスで脳に届け、騒がしい環境下でも聞き取りの向上が期待されている。さらに音の処理に、高度な人工知能(DNN)を搭載し、自然な聞こえを実現している。
サイズがコンパクトで目立ちにくいのも注目したいポイントだ。「いかにも、昔のイメージの補聴器」という見た目ではなく、スタイリッシュでカッコいいデザインなったことで、スマホやメガネなどの日常アイテムにも違和感なく馴染み、ネガティブな印象も払拭されつつあるという。
受付横のオーティコン補聴器紹介ブースには、来場者向けのアンケートが行われ、“補聴器に(高度)AIが搭載されていることを知っていますか?”という質問がされていた。結果、全回答者数の約1割が“知っている”と回答し、残りの9割は“知らなかった”と回答したという。“知らない”と回答した人の中には、「へぇー、そうなんだ、AIは何をしているの?」という質問をする人が多かったようだ。

来場者向けにアンケートを実施
今回の選手権では、オーティコンの補聴器と連携する補聴援助システム「エデュマイク」も導入されていた。これは会場マイクの音声を無線で補聴器に飛ばすための機器で、よりクリアに音声を聞き取ることができる。ただ「音が聞こえる」というだけでなく、その先の「音を聞いて楽しむ」ということまで考えているということがよく伝わってくる取り組みといえるだろう。

昨年6月に発売された「Oticon Intent(オーティコン インテント)」と
補聴援助システム「エデュマイク」

3分間で今の聴力が分かる
「簡単聞こえのチェック」のブース

簡易的な防音環境で、専用ヘッドホンと
タブレットを連携した簡単聞こえのチェックブース
簡単聞こえのチェックでは、測定結果がタブレット端末に表示され、どの周波数帯の音が聞こえにくくなっているのかを簡易的に見ることができます。実際にチェックした人からは「健康診断では再検査の要否しかしらされないが自分の聞こえを知ることができてよかった」という声や「聞こえにくくなっていることが認識できたので、ちゃんと耳鼻科に行ってみようと思う」といった声も寄せられているとのことだった。

簡単聞こえのチェック終了後には、
どの周波数帯の音が聞こえにくくなっているのか、グラフで表示される

結果を記載したプリントももらえた
聞こえの悩みは本人だけでなく、周囲の家族や友人にとっても影響を及ぼすものだ。円滑なコミュニケーションがとれなければ、他者との関わりを持つことに消極的になり、社会的活動から距離を置くようになってしまう。聞こえは悪化すると元の状態に戻るのは非常に難しい。聞こえ難さを感じたら、早めに耳鼻科を受診して、適切に聴覚ケアを行うことが重要とのことだ。
補聴援助システム「エデュマイク」を使った、補聴器ユーザーにお話を伺った。「音声がはっきりと聞こえ、落語を存分に楽しめました。お手洗いに行った時も、会場のマイク音声は補聴器に届いていました。補聴援助システムが公共の場に設置されたら、補聴器ユーザーにとってもっとバリアフリーな世の中になる気がします」と語ってくれた。
音声によるエンタテインメントはきちんと聞こえる状態を維持できれば、生涯に渡って楽しむことができるものだ。聴覚や聴覚ケアに対する意識や正しい知識がさらに広がっていくことに期待したい。(フリーライター・小倉 笑助)

「2024年度 公推協杯 全国若手落語家選手権」の本選のポスター
全国若手落語家選手権とは?
公推協杯 全国若手落語家選手権は、今回で3回目を迎える、若手落語家が話芸を競うコンクールだ。出場者は、入門15年以下の真打ちと前座の間の「二つ目」クラスの落語家が対象で、次世代のスターを育てる登竜門として注目を集めている。昨年11月から予選が合計4回行われており、2月21日の本選では各予選を勝ち抜いた柳家小ふねさん、桂源太さん、笑福亭茶光さん、三遊亭ごはんつぶさんの4人が磨き抜かれた落語を披露した。最終的には、新作落語の演目「落語業界の真実」を披露したごはんつぶさんが大賞に選ばれた。オーティコン補聴器は3回目となる24年度から本選手権を協賛しており、予選および本選会場で先進補聴器の展示や約3分で簡単に聞こえのチェックができる機器を設置したブースを出展して、聴覚ケアの啓発を行った。オーティコン補聴器の展示ブースは会場の中でも存在感があり、来場者も大いに興味を引いている様子だった。

最新モデルの実寸大レプリカの展示と、後に続く体験型ブースへの誘導を行った
オーティコン補聴器が聴覚ケアの啓発に注力する理由
オーティコン補聴器は、企業理念の“Life-Changing Technology(ライフチェンジング テクノロジー)”のもと、聞こえに悩みを抱える人たちの人生を変えるような補聴器技術の開発を日々行い、先進的な製品を販売している。難聴により他者とのコミュニケーションが低下することで、孤立や、認知機能の低下などが懸念されている昨今、聞こえづらさを放置せず、早めに適切な聴覚ケアを行うことが重要であるという。それにもかかわらず、実は日本は世界的にみて、補聴器の後進国というデータがある。欧米では難聴を自覚している人の補聴器装用率は50%を超える国もあるが、日本は15.2%(一般社団法人日本補聴器工業会「JapanTrak 2022 調査報告」)にとどまっている。
理由の一つとして挙げられるのは、補聴器に対するネガティブなイメージだ。日本では「補聴器は高齢者がするもの」という先入観が強く、本来対象となる人が装用に消極的になっている。オーティコン補聴器をフラッグシップブランドとして、展開するデマント・ジャパンではこうした状況を少しでも打破するために、昨年からBeyond15(装用率15%を超えて)というビジョンのもとに、さまざまな場所で聴覚ケアの啓発を行っている。
デマント・ジャパンの社長であり、オーティコン補聴器のプレジデントでもある、齋藤徹氏は「補聴器に対するネガティブなイメージを変えていき、もっと気軽に使ってもらえるようにしたい。適切な聴覚ケアによって、年齢を重ねても、やりたいことをあきらめず、その方らしく人生を楽しむアクティブシニアをサポートしたい」と語る。
また、「今回の協賛についても『落語が好きな皆様にいつまでも大好きな落語を楽しんでほしい、聞こえづらさを感じたら適切な聴覚ケアを行い、落語を楽しみ続けてほしい』という思いからだ」という。さらに、「情報保障の観点から、当社の補聴援助システム『エデュマイク』を会場に設置した。会場のマイク音声を互換性のある補聴器に直接とばすことができるため、補聴器ユーザーは楽に音声を聞くことができる、ユーザーの反応が楽しみだ」とも語った。

プレジデントでもある齋藤徹氏
落語ファンにとって「聞こえ」は切実な悩み
今回の協賛のきっかけは、2024年度 公推協杯全国若手落語家選手権を主催する共同通信社側からの働きかけだったそうだ。担当者の道下一郎氏は「中高年の落語ファンは前方の席を好む方が多い。これはそうしないと話がよく聞き取れないからという理由があると思う」と現場での気づきを教えてくれた。
主催する共同通信社の道下一郎氏
落語ファンにいつまでも長く落語を楽しんでほしい。そんな思いを持っていたところに、オーティコン補聴器との接点があり、お声がけをした。共同通信社とオーティコン補聴器の目指す方向が合致し、とてもいいコラボレーションにつながったという。
あまり知られていない補聴器の先進テクノロジーに注目
会場で行われていたオーティコン補聴器の取り組みをいくつか紹介したい。まずは、受付の隣に設置されていた最新モデルや補聴援助システム「エデュマイク」を展示したブースだ。ここで互換性のある補聴器を使用するユーザーは自身の補聴器と、補聴援助システム「エデュマイク」をペアリングすれば、会場のマイクの音声をダイレクトに補聴器から聞くことができる。あまり一般に知られていないが、現在の補聴器は先進テクノロジーによって大きく進化している。例えば昨年6月に発売された「Oticon Intent(オーティコン インテント)」は、無意識に行う頭や体の動き、会話活動、周囲の音響環境の四つの側面を感知するじぶんセンサー(4Dセンサー)を搭載。装用者の最も聞きたい音を自然な音のバランスで脳に届け、騒がしい環境下でも聞き取りの向上が期待されている。さらに音の処理に、高度な人工知能(DNN)を搭載し、自然な聞こえを実現している。
サイズがコンパクトで目立ちにくいのも注目したいポイントだ。「いかにも、昔のイメージの補聴器」という見た目ではなく、スタイリッシュでカッコいいデザインなったことで、スマホやメガネなどの日常アイテムにも違和感なく馴染み、ネガティブな印象も払拭されつつあるという。
受付横のオーティコン補聴器紹介ブースには、来場者向けのアンケートが行われ、“補聴器に(高度)AIが搭載されていることを知っていますか?”という質問がされていた。結果、全回答者数の約1割が“知っている”と回答し、残りの9割は“知らなかった”と回答したという。“知らない”と回答した人の中には、「へぇー、そうなんだ、AIは何をしているの?」という質問をする人が多かったようだ。

今回の選手権では、オーティコンの補聴器と連携する補聴援助システム「エデュマイク」も導入されていた。これは会場マイクの音声を無線で補聴器に飛ばすための機器で、よりクリアに音声を聞き取ることができる。ただ「音が聞こえる」というだけでなく、その先の「音を聞いて楽しむ」ということまで考えているということがよく伝わってくる取り組みといえるだろう。

補聴援助システム「エデュマイク」
聴覚ケアを一歩踏み出すきっかけになった人も
会場内で特に人気を集めていたのが、3分間で今の聞こえがチェックできる「簡単聞こえのチェック」のブースだ。左右の耳でそれぞれ音が聞こえたらボタンを押すという聴力検査は多くの方が職場の健康診断などですでに経験していると思うが、定年後、会社の健康診断を受けなくなった後は、自主的に検査を受ける人はあまりいない。またどんな音が聞こえにくくなっているのか把握している人となれば、さらに少ないだろう。
「簡単聞こえのチェック」のブース

タブレットを連携した簡単聞こえのチェックブース
簡単聞こえのチェックでは、測定結果がタブレット端末に表示され、どの周波数帯の音が聞こえにくくなっているのかを簡易的に見ることができます。実際にチェックした人からは「健康診断では再検査の要否しかしらされないが自分の聞こえを知ることができてよかった」という声や「聞こえにくくなっていることが認識できたので、ちゃんと耳鼻科に行ってみようと思う」といった声も寄せられているとのことだった。

どの周波数帯の音が聞こえにくくなっているのか、グラフで表示される

聞こえの悩みは本人だけでなく、周囲の家族や友人にとっても影響を及ぼすものだ。円滑なコミュニケーションがとれなければ、他者との関わりを持つことに消極的になり、社会的活動から距離を置くようになってしまう。聞こえは悪化すると元の状態に戻るのは非常に難しい。聞こえ難さを感じたら、早めに耳鼻科を受診して、適切に聴覚ケアを行うことが重要とのことだ。
補聴援助システム「エデュマイク」を使った、補聴器ユーザーにお話を伺った。「音声がはっきりと聞こえ、落語を存分に楽しめました。お手洗いに行った時も、会場のマイク音声は補聴器に届いていました。補聴援助システムが公共の場に設置されたら、補聴器ユーザーにとってもっとバリアフリーな世の中になる気がします」と語ってくれた。
音声によるエンタテインメントはきちんと聞こえる状態を維持できれば、生涯に渡って楽しむことができるものだ。聴覚や聴覚ケアに対する意識や正しい知識がさらに広がっていくことに期待したい。(フリーライター・小倉 笑助)