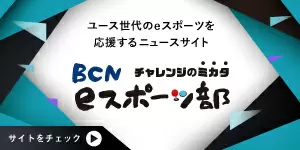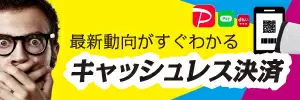AIが花盛りだ。必ずと言っていいほど毎日どこかでAIの話を見聞きする。昨年は、AI-PC元年とも言われた。ただ、我々の生活や仕事に具体的にどう役立つのかイマイチはっきりしない。各方面の「偉い人」に訊いて回ったりもしたが、どれもぼんやりとしたものばかり。なかなか明確なイメージは得られなかった。しかし、先日大阪で開かれた「dynabook Days 2025」のセミナーで、かなり具体的な活用事例を知ることができた。

「AIに半信半疑の中間管理職がCopilotを仕事で使ってみた」と題するこのセミナー。dynabookの国内マーケティング本部 国内商品開発部 国内市場分析戦略担当 宮嶋永遠 グループ長によるもの。内容は、マイクロソフトが提供する、オフィスソフトでAIを利用する有料サービス「Microsoft 365 Copilot」の活用例紹介だ。世界初のノートPCを世に送り出した同社が、35周年を記念して開催したイベントのヒトコマ。宮嶋グループ長はこう話す。「Web会議で言えば、ノイズキャンセルができるとか、背景が変えられるとか、化粧した感じにしてくれるとか、単にコンピュータが処理できる機能を、AIと言ってごまかす風潮がまん延していた」。全くその通り。これまであちこちで説明されてきた、AI活用による恩恵については「コレジャナイ感」が溢れていた。もっと具体的に仕事をどうサポートしてくれるのか、それこそ重要な部分だ。「絵なんか描いてないで、俺の仕事を手伝ってくれ」(宮嶋 グループ長)というわけだ。

dynabookの国内マーケティング本部
国内商品開発部 国内市場分析戦略担当
宮嶋永遠 グループ長
セミナーでは、イベント開催の案内文書作成でWord、製品キャンペーンのプレゼン資料作成でPowerpoint、自社製品の販売動向分析でExcelといったかたちで、AIを活用した作業例が示された。例えばWordのCopilotに対し文字を書き込んで指示。「2025年2月13日に、大阪梅田のウエスティンホテルで開催される『dynabook Days 2025 大阪』の案内を作成する。対象は企業のお客様。挨拶からはじめて、イベント概要、申し込み方法、問い合わせ先を載せてほしい」という具合だ。すると、大きな文字でタイトルを「dynabook Days 2025 大阪の案内」とした後、拝啓から始まる案内文、開催概要の箇条書きなどが続くWord文書が自動的に作られた。案内文が少々硬すぎるなら、その部分を範囲指定してもう少し砕けた感じに、と指示すると、今度は「こんにちは!……」から始まるフレンドリーな文書に書き換えてくれる。ほぼ一瞬の出来事だ。そのほか、Powerpointでは「新大学生向け dynabook X8の紹介」を作らせたり、Excelでは、ノートPCの市場規模とDynabookの出荷台数の時系列変化を並べて分析させる、といったデモも披露された。

イベントの案内文をCopilotに作らせる。
体裁も含めて取り合えず作ってくれる
もちろん、出来上がったドキュメントには、表現がおかしいところがあったり、誤った部分があったりもする。しかし、書式やデザインなど込みで「タタキ台」を作ってくれるのはとてもありがたい。ゼロから1を作るより、1を修正して10や20にする方が楽だ。自分専用のアシスタントを一人雇ったような感覚。そういえば宮嶋 グループ長もセミナー中、何度も「Copilot君」と擬人化しつつ説明していた。なるほど。まるで自分のチームに入ってきた新卒社員と仕事をするようなものじゃないか。AI活用のかなり明確なイメージが湧いてきた。新人君は仕事に対する知識や社会人経験が乏しいから間違ったり、少々変な文章だったりすることもある。しかし、大まかな流れを考えてくれて、文書やプレゼンのデザインを作ってくれれば、それはそれで大いに役立つ。経験を積めばより精度が高まっていくだろう。AIも同様だ。

Powerpointのプレゼンスライドも、文字で指示するだけで、
画像やデザインも含めてタタキ台を作ってくれる
これまではアイディア出しなど、言葉ベースでのサポートが多かったAI。しかし、Officeソフトと組み合わせて、文書のデザインや体裁なども含めて手助けしてくれれば、実務的にもかなり有用だ。何を隠そう私はPowerpointが大嫌い。アイディアを記した文書ならA4ペラ1枚で済むところを、いちいちイラストを入れたりフォントを変えたりアニメーションを入れたりして、工夫するのが、面倒くさすぎてやる気がしない。そのあたりをやってくれるなら助かる。必ずしも正確ではなかったり、全く間違ったことを自信満々に記述したり、少なからず利用料がかかったりと、AIのデメリットはもちろんある。しかし、人間がやってもさして変わらないだろう。ようやく、仕事でAIに助けてもらえる具体的な姿が見えてきたわけだ。
AIアシスタントは急速に進歩し、ほどなく仕事や生活になくてはならない存在になる。その時、人間はどうあるべきか。学校を出て企業に入る本物の新人君は、何をすべきなのか? AI活用が当たり前の時代、人々に求められる能力は何なのか? 大きな課題だ。例えば、AIでは獲得が難しい感覚的な情報を、分かりやすく扱い表現できる能力。あるいはインターネット上には存在せず、AIには収集できない情報を集める力。そんなものがあれば、人間ならではの領域を担う存在として生き残れそうだ。しかし当面、一番に求められるのは「世にあまたあるAIを縦横無尽に使いこなす力」ということになるだろう。(BCN・道越一郎)

「AIに半信半疑の中間管理職がCopilotを仕事で使ってみた」と題するこのセミナー。dynabookの国内マーケティング本部 国内商品開発部 国内市場分析戦略担当 宮嶋永遠 グループ長によるもの。内容は、マイクロソフトが提供する、オフィスソフトでAIを利用する有料サービス「Microsoft 365 Copilot」の活用例紹介だ。世界初のノートPCを世に送り出した同社が、35周年を記念して開催したイベントのヒトコマ。宮嶋グループ長はこう話す。「Web会議で言えば、ノイズキャンセルができるとか、背景が変えられるとか、化粧した感じにしてくれるとか、単にコンピュータが処理できる機能を、AIと言ってごまかす風潮がまん延していた」。全くその通り。これまであちこちで説明されてきた、AI活用による恩恵については「コレジャナイ感」が溢れていた。もっと具体的に仕事をどうサポートしてくれるのか、それこそ重要な部分だ。「絵なんか描いてないで、俺の仕事を手伝ってくれ」(宮嶋 グループ長)というわけだ。

国内商品開発部 国内市場分析戦略担当
宮嶋永遠 グループ長
セミナーでは、イベント開催の案内文書作成でWord、製品キャンペーンのプレゼン資料作成でPowerpoint、自社製品の販売動向分析でExcelといったかたちで、AIを活用した作業例が示された。例えばWordのCopilotに対し文字を書き込んで指示。「2025年2月13日に、大阪梅田のウエスティンホテルで開催される『dynabook Days 2025 大阪』の案内を作成する。対象は企業のお客様。挨拶からはじめて、イベント概要、申し込み方法、問い合わせ先を載せてほしい」という具合だ。すると、大きな文字でタイトルを「dynabook Days 2025 大阪の案内」とした後、拝啓から始まる案内文、開催概要の箇条書きなどが続くWord文書が自動的に作られた。案内文が少々硬すぎるなら、その部分を範囲指定してもう少し砕けた感じに、と指示すると、今度は「こんにちは!……」から始まるフレンドリーな文書に書き換えてくれる。ほぼ一瞬の出来事だ。そのほか、Powerpointでは「新大学生向け dynabook X8の紹介」を作らせたり、Excelでは、ノートPCの市場規模とDynabookの出荷台数の時系列変化を並べて分析させる、といったデモも披露された。

体裁も含めて取り合えず作ってくれる
もちろん、出来上がったドキュメントには、表現がおかしいところがあったり、誤った部分があったりもする。しかし、書式やデザインなど込みで「タタキ台」を作ってくれるのはとてもありがたい。ゼロから1を作るより、1を修正して10や20にする方が楽だ。自分専用のアシスタントを一人雇ったような感覚。そういえば宮嶋 グループ長もセミナー中、何度も「Copilot君」と擬人化しつつ説明していた。なるほど。まるで自分のチームに入ってきた新卒社員と仕事をするようなものじゃないか。AI活用のかなり明確なイメージが湧いてきた。新人君は仕事に対する知識や社会人経験が乏しいから間違ったり、少々変な文章だったりすることもある。しかし、大まかな流れを考えてくれて、文書やプレゼンのデザインを作ってくれれば、それはそれで大いに役立つ。経験を積めばより精度が高まっていくだろう。AIも同様だ。

画像やデザインも含めてタタキ台を作ってくれる
これまではアイディア出しなど、言葉ベースでのサポートが多かったAI。しかし、Officeソフトと組み合わせて、文書のデザインや体裁なども含めて手助けしてくれれば、実務的にもかなり有用だ。何を隠そう私はPowerpointが大嫌い。アイディアを記した文書ならA4ペラ1枚で済むところを、いちいちイラストを入れたりフォントを変えたりアニメーションを入れたりして、工夫するのが、面倒くさすぎてやる気がしない。そのあたりをやってくれるなら助かる。必ずしも正確ではなかったり、全く間違ったことを自信満々に記述したり、少なからず利用料がかかったりと、AIのデメリットはもちろんある。しかし、人間がやってもさして変わらないだろう。ようやく、仕事でAIに助けてもらえる具体的な姿が見えてきたわけだ。
AIアシスタントは急速に進歩し、ほどなく仕事や生活になくてはならない存在になる。その時、人間はどうあるべきか。学校を出て企業に入る本物の新人君は、何をすべきなのか? AI活用が当たり前の時代、人々に求められる能力は何なのか? 大きな課題だ。例えば、AIでは獲得が難しい感覚的な情報を、分かりやすく扱い表現できる能力。あるいはインターネット上には存在せず、AIには収集できない情報を集める力。そんなものがあれば、人間ならではの領域を担う存在として生き残れそうだ。しかし当面、一番に求められるのは「世にあまたあるAIを縦横無尽に使いこなす力」ということになるだろう。(BCN・道越一郎)