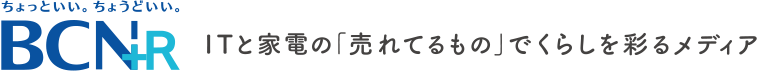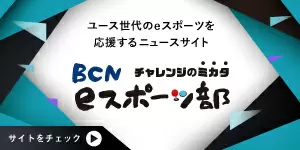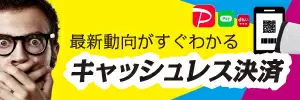決して若者とは言えない筆者が最近気になる、IDとパスワードや生体認証でログインしなければ確認できない数々のデジタルデータの自分の”死後”の扱い。そこで今回は、「今は見られたくはないけれど、万が一の時、渡したいものは渡したい」というやっかいな遺品、「デジタル遺品」の終活について考えてみる。

今は見られたくはないけれど、
万が一の時、渡したいものは渡したいというやっかいな遺品、
「デジタル遺品」
※筆者にはない、断じてない、と書いておく。
「遺品」について大辞林で調べてみると、
『死者の残したも品物』
とある。筆者は両親とも他界しているので、父の遺品、母の遺品を持っている。とはいえ、貴金属類などはまったくなく、古い本だったり、ネクタイピンだったり、着物だったり、家電製品だったり、とその程度だ。父親はスマホやPCが普及する前に死去し、つい最近亡くなった母親も、スマホのパスワードは筆者が設定したぐらいなので、デジタル遺品で困るようなことはなかった。デジタル遺品で困るようなことはなかった。

「デジタル遺品」のイメージ
どんなものがデジタル遺品になるのか、ちょっと整理してみよう。

Googleフォトには大量の写真が保存されている
この写真・動画の保管場所だが、iPhoneの中に直近2年間の写真、iCloudに2017~2022年の写真、Googleフォトには2009年から現在までのiPhoneで撮影した写真、Amazon PhotosにもGoogleフォトと同じ写真が保存されている。
これに加えてデジカメで撮った写真があるが、これは今使っているWindows PCとかつて使っていて今はストレージ機になっているiMac、それにかつてつなげていたHDDに未整理のまま保存されている。
ここ10年分の写真はいくつかのクラウドサービスに保管されているが、2000年代の写真はハードディスク内と分散状態。デジタル写真は量が膨大過ぎて、遺される家族にはけっこう困りもののデジタル遺品だろう。その上、これから死ぬまで、さらに膨大な量が積み重なっていくのは間違いない。デジタル写真は、元気な内に整理しておきたいデジタル遺品の最右翼だ。
前述の写真や動画はもちろんのこと、メールのやりとり、電話番号、スケジュール、日記、家計簿など、遺族に引き渡したい情報と遺族には見られたくない情報が混然一体となっていて、かなりやっかいである。写真ほどわかりやすく渡せないデジタル遺品になるので、まずは何を残すべきか、何を遺さないべきかについての基本方針を立てて、毎日ちょっとずつ整理しつつづけるのがよさそうだ。

大量のアカウントとパスワードがあふれている
これ、自分自身も、なにがどうなっているかもうわからなくなっている、という人が多いのではないだろうか?インターネット時代は、どんなサービスを受けるのにも、IDとパスワードでアカウントを作らないと先に進めないことが多い。
なので、
「ちょっと試してみよう」
というレベルでアカウントを作ったけれど、すぐ使わなくなった、とか、そこそこ使っていたけれど、別のより便利なサービスがでてきたのでそちらに乗り換えて、以前のサービスはそのまま放置している、といったものがいっぱいあるのだ。ただ、そんな使わなくなったアカウントは、遺族にとっても重要ではないだろうから、いったんはそのままにしておこう。
最も重要なアカウントは、お金に関するものだ。これはデジタル「遺産」にも関係するので、自分の目の黒い内にまとめておいた方がよい。
具体的には、銀行のアカウント、証券会社のアカウント、クレジットカードのアカウント、電子マネーのアカウントなどだ。リアル店舗のある銀行であれば通帳と印鑑で資産と引き継げるが、ネット銀行の口座を持っている場合は、IDとパスワードが通帳と印鑑がわりだ。証券会社もネット証券の口座であれば同じようにIDとパスワードが重要になる。クレジットカードは使用しているカード会社と利用を止めるための方法をしっかりと遺しておきたい。電子マネーは残高が少額なものが多いとは思うが、お金には違いないので一応、アカウントを引き渡せるようにしておこう。
次に重要なアカウントはサブスクリプション系のサービスだ。これは、放置しているとずっとお金を引き落とされ続けるので、サービスを解約するためにも、アカウントと解約方法を遺しておきたい。
時々、SNSの投稿で
「このアカウントの〇〇が代理で投稿しております。★★は●月●日、この世を旅立ちました……」
というような文章を見かけることがある。おそらく、不治の病を患った方が、自分の死後に、フォロワーにお知らせしてほしい、という遺言と共にIDとパスワードを遺族に託したのだろう。不慮の事故での突然死に備えて、今使っているSNSとアカウント、万が一死んだ時の対処方法などを遺しておくと、気持ちが楽になるかもしれない。

国民生活センターも「デジタル遺品」について、
生前の整理リスト作成を呼びかけている
今回はここまで。後編では、筆者が提案するジャンル別デジタル遺品整理法をカテゴリごとに紹介していく。
■Profile
西脇 功
3Dデザイナーズスクール(https://3dschool.jp/)学長。製薬会社勤務を経て、1987年にApple社のMacintoshに出会いコンピュータ業界へと転進。IT系企業数社でコンテンツマーケティング、広報・宣伝のプロとして活動。製品導入事例の執筆、オウンドメディアのWebサイト立ち上げからコンテンツ作成までを一人で担当。2020年独立し、合同会社「天使の時間」を設立。3DCGソフト活用のためのオンラインスクール運営や、Webメディアへの記事執筆を行っている。

万が一の時、渡したいものは渡したいというやっかいな遺品、
「デジタル遺品」
デジタル遺品とは?
まずはデジタル遺品について、整理しておこうと思った。スマートフォン(スマホ)、パソコン(PC)、クラウド、と誰もがあちこちにデジタルデータを保管している時代である。もし、事故などで不慮の死を迎えた時、これらの所有物は残された人たちには目に見えないという点がやっかいだ。しかも、生きている間は、見られたくはないものも人によってはあるだろう。※筆者にはない、断じてない、と書いておく。
「遺品」について大辞林で調べてみると、
『死者の残したも品物』
とある。筆者は両親とも他界しているので、父の遺品、母の遺品を持っている。とはいえ、貴金属類などはまったくなく、古い本だったり、ネクタイピンだったり、着物だったり、家電製品だったり、とその程度だ。父親はスマホやPCが普及する前に死去し、つい最近亡くなった母親も、スマホのパスワードは筆者が設定したぐらいなので、デジタル遺品で困るようなことはなかった。デジタル遺品で困るようなことはなかった。

どんなものがデジタル遺品になるのか、ちょっと整理してみよう。
写真・動画
まずは写真・動画だろう。写真のプリントなどを行っているイギリスの企業「Max Spielmann」によると、2023年に人類が1秒間に撮影した写真は5万4400枚だそうだ。ちなみに筆者のGoogleフォトには約3万6000枚の写真が保管されている。
この写真・動画の保管場所だが、iPhoneの中に直近2年間の写真、iCloudに2017~2022年の写真、Googleフォトには2009年から現在までのiPhoneで撮影した写真、Amazon PhotosにもGoogleフォトと同じ写真が保存されている。
これに加えてデジカメで撮った写真があるが、これは今使っているWindows PCとかつて使っていて今はストレージ機になっているiMac、それにかつてつなげていたHDDに未整理のまま保存されている。
ここ10年分の写真はいくつかのクラウドサービスに保管されているが、2000年代の写真はハードディスク内と分散状態。デジタル写真は量が膨大過ぎて、遺される家族にはけっこう困りもののデジタル遺品だろう。その上、これから死ぬまで、さらに膨大な量が積み重なっていくのは間違いない。デジタル写真は、元気な内に整理しておきたいデジタル遺品の最右翼だ。
スマホのデータ(アプリなど)
いまやスマホには、ありとあらゆる個人データがぎっしりと詰まっている。前述の写真や動画はもちろんのこと、メールのやりとり、電話番号、スケジュール、日記、家計簿など、遺族に引き渡したい情報と遺族には見られたくない情報が混然一体となっていて、かなりやっかいである。写真ほどわかりやすく渡せないデジタル遺品になるので、まずは何を残すべきか、何を遺さないべきかについての基本方針を立てて、毎日ちょっとずつ整理しつつづけるのがよさそうだ。

これ、自分自身も、なにがどうなっているかもうわからなくなっている、という人が多いのではないだろうか?インターネット時代は、どんなサービスを受けるのにも、IDとパスワードでアカウントを作らないと先に進めないことが多い。
なので、
「ちょっと試してみよう」
というレベルでアカウントを作ったけれど、すぐ使わなくなった、とか、そこそこ使っていたけれど、別のより便利なサービスがでてきたのでそちらに乗り換えて、以前のサービスはそのまま放置している、といったものがいっぱいあるのだ。ただ、そんな使わなくなったアカウントは、遺族にとっても重要ではないだろうから、いったんはそのままにしておこう。
最も重要なアカウントは、お金に関するものだ。これはデジタル「遺産」にも関係するので、自分の目の黒い内にまとめておいた方がよい。
具体的には、銀行のアカウント、証券会社のアカウント、クレジットカードのアカウント、電子マネーのアカウントなどだ。リアル店舗のある銀行であれば通帳と印鑑で資産と引き継げるが、ネット銀行の口座を持っている場合は、IDとパスワードが通帳と印鑑がわりだ。証券会社もネット証券の口座であれば同じようにIDとパスワードが重要になる。クレジットカードは使用しているカード会社と利用を止めるための方法をしっかりと遺しておきたい。電子マネーは残高が少額なものが多いとは思うが、お金には違いないので一応、アカウントを引き渡せるようにしておこう。
次に重要なアカウントはサブスクリプション系のサービスだ。これは、放置しているとずっとお金を引き落とされ続けるので、サービスを解約するためにも、アカウントと解約方法を遺しておきたい。
SNS
アカウントとパスワードの一種ではあるが、前述のようなお金関連ではないので、すぐにどうこうしなくてはならないものではないだろう。だが、自分と社会をつないでいたものではあるので、自分の死後にどうしたいかは考えておきたい。時々、SNSの投稿で
「このアカウントの〇〇が代理で投稿しております。★★は●月●日、この世を旅立ちました……」
というような文章を見かけることがある。おそらく、不治の病を患った方が、自分の死後に、フォロワーにお知らせしてほしい、という遺言と共にIDとパスワードを遺族に託したのだろう。不慮の事故での突然死に備えて、今使っているSNSとアカウント、万が一死んだ時の対処方法などを遺しておくと、気持ちが楽になるかもしれない。

生前の整理リスト作成を呼びかけている
今回はここまで。後編では、筆者が提案するジャンル別デジタル遺品整理法をカテゴリごとに紹介していく。
■Profile
西脇 功
3Dデザイナーズスクール(https://3dschool.jp/)学長。製薬会社勤務を経て、1987年にApple社のMacintoshに出会いコンピュータ業界へと転進。IT系企業数社でコンテンツマーケティング、広報・宣伝のプロとして活動。製品導入事例の執筆、オウンドメディアのWebサイト立ち上げからコンテンツ作成までを一人で担当。2020年独立し、合同会社「天使の時間」を設立。3DCGソフト活用のためのオンラインスクール運営や、Webメディアへの記事執筆を行っている。