リコーの「PENTAX」買収、コンシューマ事業の確立に邁進するリコーの思惑
リコーが、HOYAのPENTAXイメージング・システム事業の買収を発表した。リコーの近藤史朗社長は、記者会見で「3年で1000億円の売上規模を目指す」と表明したが、デジカメ業界8位のPENTAX(HOYA)と9位のリコーが、なぜいま一つになることを選択したのか。その背景を読む。
まず、HOYAの内情から紐解いていこう。HOYAがTOB(株式公開買付け)によってペンタックスを買収したのは2007年。ただ、このTOBは、HOYAの本意ではなかった。本来は2007年10月をめどにHOYAがペンタックスを吸収合併する予定だったが、カメラ事業売却の懸念を抱いたペンタックス取締役の過半数が合併に反対。2007年4月9日、当時ペンタックス社長だった浦野文男氏をはじめ役員が退任して、合併を白紙に戻した。
そこでHOYAはTOBによるペンタックスの買収・子会社化を発表。2007年7月3日から8月6日までTOBを実施し、発行株式の90.59%を944億8200万円で取得した。この一連の流れは、敵対的TOBに近いといえるだろう。実際、今回の記者会見では、HOYAの鈴木洋CEOが当時を振り返り、「(統合後は)そこそこうまくいった」と説明はしたものの「苦労もあった」と漏らしている。また、「ある意味、ほっとしている面もある」とも表現していた。
一方のリコーは、「PENTAXのデジカメ事業がお嫁にきてくれるようなもの」(近藤社長)と大歓迎。買収の経緯は、「2年前に、どちらともなく会いたいということになって、『こんなカメラをつくりたい』と話した」(近藤社長)。これに対してHOYAの鈴木CEOは、「(リコーの近藤社長は)カメラを理解しているし、大事にしてくれる。喜んで嫁に出せる」と判断。「一つの区切りがついた」(鈴木CEO)ことから、今回の買収が合意に至った。
では、なぜリコーはPENTAXを買収したのか。それは、リコーのなかで「コンシューマ事業の確立が課題になっている」(近藤社長)から。まずは、これまで手がけてきたデジカメを安定した事業として成長させ、次のステップとして「ストレージを含めた事業領域の拡大に取り組んでいく」(近藤社長)方針だ。
リコーは、オンラインストレージサービス「quanp(クオンプ)」を提供している。入力機器であるデジカメ事業を拡大することで、撮影した写真データを「quanp」に保存、出力機器のプリンタやプロジェクターなどを利用するといったサイクルを構築することで、リコーの強みを生かしていく目論見だ。
また、近藤社長は「コンシューマ向けにネットワークにつながるアプライアンスの発売を模索している」としており、ホームネットワークを切り口に「新しい世界をつくっていきたい」という。そのきっかけとして、「(これまでも手がけていることから)コンシューマ事業を確立するには、デジカメが入りやすい」との考えもある。
さらに近藤社長は、「リコーのカメラは、カメラ好きがつくっている。しかし、もう少しビジネスにしなければならない」という現状認識を披露した。PENTAXの買収でカメラ事業に長けた人材が増えることになるわけだが、リコー関係者は「社長は、『新卒を含めてよい人材を採用していくには、コンシューマブランドの向上が重要』と話している」と打ち明けた。ブランドの確立によって、人材の質を高めることも視野に入れているようだ。
リコーのPENTAX買収には、このように、リコーが描くいくつかの思惑が横たわっている。そして近藤社長は、「事業の規模を追うわけではない」とも語っている。老舗のカメラブランドとして、長年にわたって記憶に残る個性的な名機を数多く世に送り出してきたリコーとPENTAX。熱烈なファンも多い。今回の買収で、リコーが企図するコンシューマ事業の確立は、いつ実現するのか。そして、ユーザーの期待に応える製品はいつ出るのか。期待しながら注目したい。(BCN・佐相彰彦)
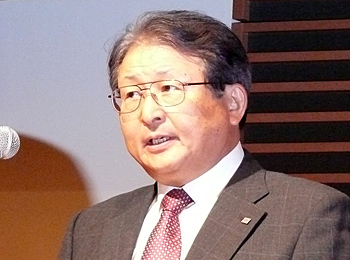
PENTAXの買収で事業拡大に意欲を燃やすリコーの近藤史朗社長
まず、HOYAの内情から紐解いていこう。HOYAがTOB(株式公開買付け)によってペンタックスを買収したのは2007年。ただ、このTOBは、HOYAの本意ではなかった。本来は2007年10月をめどにHOYAがペンタックスを吸収合併する予定だったが、カメラ事業売却の懸念を抱いたペンタックス取締役の過半数が合併に反対。2007年4月9日、当時ペンタックス社長だった浦野文男氏をはじめ役員が退任して、合併を白紙に戻した。
そこでHOYAはTOBによるペンタックスの買収・子会社化を発表。2007年7月3日から8月6日までTOBを実施し、発行株式の90.59%を944億8200万円で取得した。この一連の流れは、敵対的TOBに近いといえるだろう。実際、今回の記者会見では、HOYAの鈴木洋CEOが当時を振り返り、「(統合後は)そこそこうまくいった」と説明はしたものの「苦労もあった」と漏らしている。また、「ある意味、ほっとしている面もある」とも表現していた。

HOYAの鈴木洋CEO
一方のリコーは、「PENTAXのデジカメ事業がお嫁にきてくれるようなもの」(近藤社長)と大歓迎。買収の経緯は、「2年前に、どちらともなく会いたいということになって、『こんなカメラをつくりたい』と話した」(近藤社長)。これに対してHOYAの鈴木CEOは、「(リコーの近藤社長は)カメラを理解しているし、大事にしてくれる。喜んで嫁に出せる」と判断。「一つの区切りがついた」(鈴木CEO)ことから、今回の買収が合意に至った。

HOYAとリコーががっちりと握手。今回の買収は友好的
では、なぜリコーはPENTAXを買収したのか。それは、リコーのなかで「コンシューマ事業の確立が課題になっている」(近藤社長)から。まずは、これまで手がけてきたデジカメを安定した事業として成長させ、次のステップとして「ストレージを含めた事業領域の拡大に取り組んでいく」(近藤社長)方針だ。
リコーは、オンラインストレージサービス「quanp(クオンプ)」を提供している。入力機器であるデジカメ事業を拡大することで、撮影した写真データを「quanp」に保存、出力機器のプリンタやプロジェクターなどを利用するといったサイクルを構築することで、リコーの強みを生かしていく目論見だ。
また、近藤社長は「コンシューマ向けにネットワークにつながるアプライアンスの発売を模索している」としており、ホームネットワークを切り口に「新しい世界をつくっていきたい」という。そのきっかけとして、「(これまでも手がけていることから)コンシューマ事業を確立するには、デジカメが入りやすい」との考えもある。
さらに近藤社長は、「リコーのカメラは、カメラ好きがつくっている。しかし、もう少しビジネスにしなければならない」という現状認識を披露した。PENTAXの買収でカメラ事業に長けた人材が増えることになるわけだが、リコー関係者は「社長は、『新卒を含めてよい人材を採用していくには、コンシューマブランドの向上が重要』と話している」と打ち明けた。ブランドの確立によって、人材の質を高めることも視野に入れているようだ。
リコーのPENTAX買収には、このように、リコーが描くいくつかの思惑が横たわっている。そして近藤社長は、「事業の規模を追うわけではない」とも語っている。老舗のカメラブランドとして、長年にわたって記憶に残る個性的な名機を数多く世に送り出してきたリコーとPENTAX。熱烈なファンも多い。今回の買収で、リコーが企図するコンシューマ事業の確立は、いつ実現するのか。そして、ユーザーの期待に応える製品はいつ出るのか。期待しながら注目したい。(BCN・佐相彰彦)






