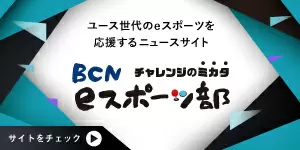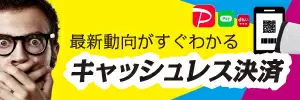マイナンバーカードでできることまとめ 3月24日から運転免許証との一体化が開始
マイナンバーが記載された顔写真付のカード「マイナンバーカード」。さまざまな機能が整いはじめ、非常に便利なカードになりつつあります。かつてはマイナポイントの配布もあり、すでに所持している人も多いのではないでしょうか。

一方でマイナンバーカードはまだまだ発展段階。すでにできること、これからできるようになることが多数混在しています。本記事では健康保険証などをはじめとして「マイナンバーカードでできること」について紹介します。
マイナンバー制度導入後、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害など、多くの場面で個人番号の提示が必要となっています。マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と本人確認が可能となり、複数の確認書類がいらなくなります。
本人確認(対面)
本人確認(オンライン)
コンビニでの書類交付
健康保険証として
運転免許証として
住民票の写し
住民票記載事項証明
印鑑登録証明
各種税証明
戸籍
戸籍(本籍地)
戸籍の附票
戸籍の附票(本籍地)
なお、自治体によって発行できる証明書には違いがあります。もし利用する場合は下記公式サイトからコンビニ交付サービスに対応しているか確認しましょう。
コンビニ交付 利用できる市区町村
では実際に証明書を取得する方法を紹介しましょう。
まず最初に、店舗に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押すと、利用開始となります。

端末の画面イメージ
その後、利用上の同意事項が表示されますので、「同意する」を選択して進むとコンビニ交付サービスを利用できるようになります。ただし、交付の際にはマイナンバーカードの暗証番号や交付手数料がかかりますので事前に準備しておきましょう。

マイナンバーカードのメリット
なお、現行の健康保険証の発行は24年12月2日時点で終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間まで有効という経過措置が取られますが、それ以降は使えなくなってしまうので、もしまだマイナンバーカードを持っていないという人は早めに取得した方がよいかもしれません。

一体化の開始後はマイナンバー運転免許証(マイナ免許証)と通常の運転免許証の二種類が存在することとなり、二つの免許証を一緒に保有することも可能です。そのため、3月24日以降の運転免許証の保有形態は、マイナ免許証単独、通常の運転免許証単独、両者を共に保有の三形態となります。
続いてマイナ免許証のメリットについて解説します。主なメリットは下記の通り
免許更新時のオンライン講習
住所変更手続きなどの簡略化
免許更新手数料が安くなる
免許更新時のオンライン講習
マイナ免許証を持っており、必要な手続きを済ませている人は運転免許証を更新するときに必要になる講習をオンラインで受講することができるようになります。免許センターなどに出向く必要がなく、都合のいい時間に受講できるため、わざわざ「休みを取って更新」といった手間がありません。
住所変更手続きなどの簡略化
マイナ免許証を持っていて、必要な手続きをした人は、本籍や住所、氏名などが変わったときの警察への届け出がいらなくなります。これは、マイナンバーカードと運転免許証の情報を紐づけることで可能になるサービスで、マイナンバーカードの情報を最新に更新していれば、それに紐づいたマイナ免許証の情報も同期されるという仕組みです。
免許更新手数料が安くなる
運転免許証を更新する際、更新手数料と講習手数料がかかります。マイナ免許証の導入に際して、これらの手数料が改定されることが決まっており、更新後の保有形態に応じて料金が変わることがわかっています。具体的な料金は下記の通り。

出典:警視庁「マイナ免許証に伴う手数料改定」
表を参考に一例をあげると、もし「一般」の人が講習を会場で受講し、これまで通りの免許証に更新する場合は下記の金額になります。
800円+2850円=3650円
一方、「一般」の人が講習をオンラインで受講し、マイナ免許証に更新する場合は下記の菌が気になります。
200円+2100円=2300円
以上の点から、手間や費用の面でマイナ免許証の方が便利でお得になると言えます。

ここでは、すでにマイナンバーカードを取得している場合に、健康保険証として利用するための登録方法を紹介します。
まず、登録方法は下記の3通りです。
1.顔認証付きカードリーダーからの申請
2.マイナポータルからの申請
3.セブン銀行ATMからの申請
1.顔認証付きカードリーダーからの申請
最も簡単な登録方法が、「顔認証付きカードリーダーからの申請」です。この顔認証付きカードリーダーとは、全国の医療機関や薬局に置いてある機器のことで、マイナンバーで受け付けする際に使用するものです。このカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証などの本人確認をした後、保険証登録をしていない場合は登録をするかどうかを選択する画面が表示されます。ここで「登録する」を選択すると完了です。
2.マイナポータルからの申請
持っているスマートフォンがNFC読み取りに対応している機種の場合、マイナポータルのアプリやブラウザから登録する方法があります。ここでは、アプリから登録する方法を紹介します。
まずは、スマートフォンとマイナンバーカード、カード作成時に設定した4桁の暗証番号を用意しましょう。スマホの機種によってApp store(iPhone)かGoogle Play(Android)からマイナポータルのアプリをダウンロードします。アプリを開くと、ログイン画面になるので、4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取ります。ユーザー画面が表示されるので、そこで「登録状況の確認」の欄で「確認」ボタンを押すと、公金受取口座と健康保険証の登録状況が表示され、まだ健康保険証の登録がされていない場合は赤文字で「未登録」と表示されます。「未登録」ボタンを押し、次の画面で登録ボタンを押すことで登録可能です。
3.セブン銀行ATMからの申請
最後に、セブン銀行ATMでの登録方法を説明します。最初のATM画面で「各種お手続き」を選択し、「マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み」を押します。その後、利用規約に同意し、マイナンバーカードをATMに挿入、4桁の暗証番号を入力します。認証されたら登録は終了で、マイナンバーカードと利用明細書が出てくるので、忘れずに回収しましょう。

一方でマイナンバーカードはまだまだ発展段階。すでにできること、これからできるようになることが多数混在しています。本記事では健康保険証などをはじめとして「マイナンバーカードでできること」について紹介します。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真などが表示されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Taxといった電子証明書を利用した電子申請など、さまざまなサービスにも利用できます。マイナンバー制度導入後、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害など、多くの場面で個人番号の提示が必要となっています。マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と本人確認が可能となり、複数の確認書類がいらなくなります。
マイナンバーカードでできること
ここでは、マイナンバーカードで実現できるメリットを紹介します。主な内容は下記の通り。本人確認(対面)
本人確認(オンライン)
コンビニでの書類交付
健康保険証として
運転免許証として
本人確認(対面)
顔写真付きの本人確認書類として利用できます。市町村では厳格な本人確認を行っており、これに対して確実に本人であるという証として提示することができます。しかも顔写真があるので、なりすましができません。マイナンバーカードを持っていれば、公私ともに本人確認に対応できるようになります。本人確認(オンライン)
ICチップが搭載されているマイナンバーカードは、インターネットを通じてどこからでも安全・確実に本人を証明することができます。電子証明書を使って、全国のコンビニで住民票の写しなどを受け取れるほか、口座開設などの大切な手続も、どこからでも安全に行うことができます。コンビニでの書類交付
全国のコンビニに設置されているマルチコピー機にマイナンバーカードをかざせば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を受け取れます。実際に発行できる証明書は次の通り。住民票の写し
住民票記載事項証明
印鑑登録証明
各種税証明
戸籍
戸籍(本籍地)
戸籍の附票
戸籍の附票(本籍地)
なお、自治体によって発行できる証明書には違いがあります。もし利用する場合は下記公式サイトからコンビニ交付サービスに対応しているか確認しましょう。
コンビニ交付 利用できる市区町村
では実際に証明書を取得する方法を紹介しましょう。
まず最初に、店舗に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押すと、利用開始となります。

その後、利用上の同意事項が表示されますので、「同意する」を選択して進むとコンビニ交付サービスを利用できるようになります。ただし、交付の際にはマイナンバーカードの暗証番号や交付手数料がかかりますので事前に準備しておきましょう。
健康保険証として
手続きを行えば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。例えば通院している際、「受け付けでは顔認証で自動化」「正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる」「窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要」などのメリットがあります。そのほか、特定検診や薬の情報を行政手続のオンライン窓口「マイナポータル」で閲覧できるというメリットもあります。
なお、現行の健康保険証の発行は24年12月2日時点で終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間まで有効という経過措置が取られますが、それ以降は使えなくなってしまうので、もしまだマイナンバーカードを持っていないという人は早めに取得した方がよいかもしれません。
運転免許証として
2025年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証・運転経歴証明書の一体化が開始します。警視庁のwebサイトで予約し、一体化することでマイナンバーカードを運転免許証として使えるほかさまざまなメリットがあります。
一体化の開始後はマイナンバー運転免許証(マイナ免許証)と通常の運転免許証の二種類が存在することとなり、二つの免許証を一緒に保有することも可能です。そのため、3月24日以降の運転免許証の保有形態は、マイナ免許証単独、通常の運転免許証単独、両者を共に保有の三形態となります。
続いてマイナ免許証のメリットについて解説します。主なメリットは下記の通り
免許更新時のオンライン講習
住所変更手続きなどの簡略化
免許更新手数料が安くなる
免許更新時のオンライン講習
マイナ免許証を持っており、必要な手続きを済ませている人は運転免許証を更新するときに必要になる講習をオンラインで受講することができるようになります。免許センターなどに出向く必要がなく、都合のいい時間に受講できるため、わざわざ「休みを取って更新」といった手間がありません。
住所変更手続きなどの簡略化
マイナ免許証を持っていて、必要な手続きをした人は、本籍や住所、氏名などが変わったときの警察への届け出がいらなくなります。これは、マイナンバーカードと運転免許証の情報を紐づけることで可能になるサービスで、マイナンバーカードの情報を最新に更新していれば、それに紐づいたマイナ免許証の情報も同期されるという仕組みです。
免許更新手数料が安くなる
運転免許証を更新する際、更新手数料と講習手数料がかかります。マイナ免許証の導入に際して、これらの手数料が改定されることが決まっており、更新後の保有形態に応じて料金が変わることがわかっています。具体的な料金は下記の通り。

表を参考に一例をあげると、もし「一般」の人が講習を会場で受講し、これまで通りの免許証に更新する場合は下記の金額になります。
800円+2850円=3650円
一方、「一般」の人が講習をオンラインで受講し、マイナ免許証に更新する場合は下記の菌が気になります。
200円+2100円=2300円
以上の点から、手間や費用の面でマイナ免許証の方が便利でお得になると言えます。
マイナンバーカードの保険証利用登録

ここでは、すでにマイナンバーカードを取得している場合に、健康保険証として利用するための登録方法を紹介します。
まず、登録方法は下記の3通りです。
1.顔認証付きカードリーダーからの申請
2.マイナポータルからの申請
3.セブン銀行ATMからの申請
1.顔認証付きカードリーダーからの申請
最も簡単な登録方法が、「顔認証付きカードリーダーからの申請」です。この顔認証付きカードリーダーとは、全国の医療機関や薬局に置いてある機器のことで、マイナンバーで受け付けする際に使用するものです。このカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証などの本人確認をした後、保険証登録をしていない場合は登録をするかどうかを選択する画面が表示されます。ここで「登録する」を選択すると完了です。
2.マイナポータルからの申請
持っているスマートフォンがNFC読み取りに対応している機種の場合、マイナポータルのアプリやブラウザから登録する方法があります。ここでは、アプリから登録する方法を紹介します。
まずは、スマートフォンとマイナンバーカード、カード作成時に設定した4桁の暗証番号を用意しましょう。スマホの機種によってApp store(iPhone)かGoogle Play(Android)からマイナポータルのアプリをダウンロードします。アプリを開くと、ログイン画面になるので、4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み取ります。ユーザー画面が表示されるので、そこで「登録状況の確認」の欄で「確認」ボタンを押すと、公金受取口座と健康保険証の登録状況が表示され、まだ健康保険証の登録がされていない場合は赤文字で「未登録」と表示されます。「未登録」ボタンを押し、次の画面で登録ボタンを押すことで登録可能です。
3.セブン銀行ATMからの申請
最後に、セブン銀行ATMでの登録方法を説明します。最初のATM画面で「各種お手続き」を選択し、「マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み」を押します。その後、利用規約に同意し、マイナンバーカードをATMに挿入、4桁の暗証番号を入力します。認証されたら登録は終了で、マイナンバーカードと利用明細書が出てくるので、忘れずに回収しましょう。