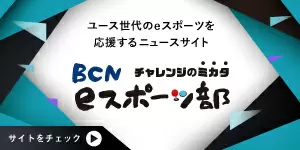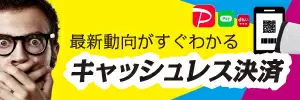【家電コンサルのお得な話・245】2025年4月1日、個人(預貯金者)が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座(銀行口座)にマイナンバーを付番できる「預貯金口座付番制度」が全面開始となった。この制度は「公金受取口座登録制度」と同様、任意、つまり利用しても利用しなくてもどちらでも良い制度だが、利用すると万が一の被災時や、本人が死去したのち、子どもや配偶者などが相続手続きをする際に負担が減るので、リスク管理の一環として活用を検討する価値はあるといえるだろう。

相続時や災害時の手続きが楽になる制度がスタート

新制度のメリットは三つ。
預貯金本人にとっては二つとなる
もともとこの制度は2018年からスタートしていたが、今年4月1日から一つの金融機関の窓口において複数の金融機関にまたがる口座の照会が可能となる仕組みが加わったことで、ようやく実用的な制度として本格稼働し始めた印象である。

マイナンバーに関する「よくある質問と答え」より
なお、現在対象外の金融機関も、一部を除き、今年度中に順次対応する予定だ。ただし、仕組み上、金融機関に届けている住所と住民票の住所が一致しない場合などは登録できない。

2025年4月1日から、
一度にすべての預貯金口座にマイナンバーを附番可能になった
一方、公金受取口座登録制度は、主に自治体などからの給付金を迅速に受け取るための仕組みであり、登録先は国(デジタル庁)である。前述の預貯金口座付番制度の届け出先は金融機関であり、そもそも制度の目的が異なる。両者は混同されやすいが、利用者にとっては「どこに何のために登録するのか」を正確に理解することが大切である。
預貯金口座付番制度を利用する最大のメリットは、相続や災害といった非常時における利便性にある。たとえば家族が亡くなった際、複数の金融機関にまたがる口座の有無を一括で確認できれば、相続人の負担は大きく軽減される。また、大規模な災害が起きた際、口座番号が記載された通帳や印鑑(銀行印)を紛失してもマイナンバーを通じて口座の所在を確認できれば、災害時の支援金の振込や復旧の手続きが格段に早まるだろう。こうした「もしも」の時の備えとしては、合理的な仕組みである。
とはいえ、制度の利用にあたり、慎重な視点も必要である。マイナンバーと紐づけることで「資産が監視されるのでは」と不安を抱く人もいるだろう(実際には、預貯金口座への付番をきっかけに、金融機関が国や自治体に対し残高を知らせることはない)。近年の政府には国民の期待を裏切る対応が目立ち、金融機関の不祥事も報じられている。こうした状況において、新しい制度には丁寧な説明と透明性が欠かせない。結局のところ、こうした制度が社会に広く根づくかどうかは、政府や金融機関の「信用」にかかっている。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_09
受付時間 平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

「公金受取口座登録制度」とは全く異なる仕組み 届け出先は金融機関
本人の同意のうえ、マイナンバーと銀行口座をひも付ける預貯金口座付番制度は、災害時や相続時に銀行口座の所在を一括で確認できるようにすることを目的としており、4月1日から、金融機関や「マイナポータル」でマイナンバーを届け出ると、一度に複数の対象金融機関の口座に登録できるようになった。
預貯金本人にとっては二つとなる
もともとこの制度は2018年からスタートしていたが、今年4月1日から一つの金融機関の窓口において複数の金融機関にまたがる口座の照会が可能となる仕組みが加わったことで、ようやく実用的な制度として本格稼働し始めた印象である。

なお、現在対象外の金融機関も、一部を除き、今年度中に順次対応する予定だ。ただし、仕組み上、金融機関に届けている住所と住民票の住所が一致しない場合などは登録できない。

一度にすべての預貯金口座にマイナンバーを附番可能になった
一方、公金受取口座登録制度は、主に自治体などからの給付金を迅速に受け取るための仕組みであり、登録先は国(デジタル庁)である。前述の預貯金口座付番制度の届け出先は金融機関であり、そもそも制度の目的が異なる。両者は混同されやすいが、利用者にとっては「どこに何のために登録するのか」を正確に理解することが大切である。
預貯金口座付番制度を利用する最大のメリットは、相続や災害といった非常時における利便性にある。たとえば家族が亡くなった際、複数の金融機関にまたがる口座の有無を一括で確認できれば、相続人の負担は大きく軽減される。また、大規模な災害が起きた際、口座番号が記載された通帳や印鑑(銀行印)を紛失してもマイナンバーを通じて口座の所在を確認できれば、災害時の支援金の振込や復旧の手続きが格段に早まるだろう。こうした「もしも」の時の備えとしては、合理的な仕組みである。
とはいえ、制度の利用にあたり、慎重な視点も必要である。マイナンバーと紐づけることで「資産が監視されるのでは」と不安を抱く人もいるだろう(実際には、預貯金口座への付番をきっかけに、金融機関が国や自治体に対し残高を知らせることはない)。近年の政府には国民の期待を裏切る対応が目立ち、金融機関の不祥事も報じられている。こうした状況において、新しい制度には丁寧な説明と透明性が欠かせない。結局のところ、こうした制度が社会に広く根づくかどうかは、政府や金融機関の「信用」にかかっている。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)
デジタル庁ホームページ
よくある質問:預貯金口座付番制度についてhttps://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_09
本件についてのお問合せ
フリーダイヤル 0120-95-0178受付時間 平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
■Profile
堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。