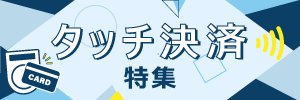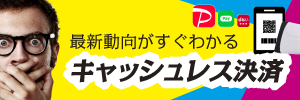モバイルオーダーの現状とこれから、飲食店にはなくてならない存在に
【外食業界のリアル・17】外食業界では、モバイルオーダーの導入が加速している。コロナが明けてから需要は一気に戻って飲食店が賑わうようになってきたが、依然として人手不足が深刻だ。「オーダーをとる」という業務をデジタル化することで、スタッフの負荷を大幅に下げることができ、今では飲食店にはなくてならない存在になりつつさえある。今回は、そのモバイルオーダーについて現状とこれからについて語りたいと思う。

「店外」は店外からの注文をメインとなるが、テイクアウトやデリバリーが主となる。テイクアウトであれば注文後に指定された時間に店舗へ受け取りに行く形となり、デリバリーであれば登録された住所にライダーが商品を運んできてくれる。
Uber Eatsや出前館、Woltなどのデリバリーメディアからの注文一元管理機能に特化したサービスもある。店舗では複数のデリバリーメディアを利用することが多いが、各社ごとに専用のタブレット端末が支給されるため、注文管理が煩雑となって商品の準備が漏れてライダーとトラブルになることもある。そのため、混雑時の店内でいかにオペレーションを回せるのかを考慮した機能が多い。
また最近では、UberDirectのようにライダーだけを提供するサービスも増えている。マネジメントやコスト上のネックとなるライダーだけをかりて、自社でデリバリーを実現できるわけである。
「店内」は店中からの注文がメインとなるが、世間一般で「モバイルオーダー」と呼ぶものはこちらを指すことが多い。店内に設置された2次元コードから自身のスマホで注文画面にアクセスして利用し、注文はPOS端末と連携されてそのまま会計できるのが一般的である。
外食企業ではLINE公式アカウントをCRMに活用するケースが多く、モバイルオーダーをLINEミニアプリ化することで、注文時に「お友達」を増やしていく形にする店舗も増えている。店外と比べると、システムとして求められる技術要件は高いといえる。
店内では営業中の注文が入り続けるため注文件数が圧倒的に多く、特に食べ放題店舗で繁忙時間帯に桁違いの量となる。しかもスタッフがハンディ端末から注文したものも共有したり、POSとの商品やクーポン、会計などの各種情報をAPIで連携したりしなくてはならない。
ほかにも店内でモバイルオーダーがPOS端末と同一ネットワーク内で動かす必要があり、想定外のことも起きる。広い店舗では回線が弱かったり、無料Wi-Fiと共有されていて不安定になったりと、ネットワークの整備も必要となることが少なくないが、複数ベンダーが絡んでいることで、どの会社がどこまで何を調整していくのかの線引きは曖昧になりがちである。
注文管理は、店舗が忙しい中でもミスなくオペレーションできることを追求している。スタッフごとに表示する商品を分け、キッチンモニターやプリンター印字など、各社によって機能差がある。
商品/オプション設定は、登録や在庫管理などの運用をどれだけ簡易にできるのかが重要だ。POSとの商品を連携させなくてはならないが、POS端末もメーカーや種類によって仕様が異なるため、モバイルオーダーとしてどのように処理をするのかは重要となってくる。
分析とCRMについては、各ベンダーが力を入れている領域となる。店舗の状態をどのように見える化するのか、再来訪・再購買を促していくために誰にどんなメッセージを配信していくのかが重要となる。このあたりも、ベンダーによる機能差は大きいところとなる。
店舗のオペレーションは混雑状況で使用されるため、予想外のことが起きることが少なくない。机上の空論で設計しても実際の店舗では使えないみたいなことが平気で起きるが、これは飲食DX全般に共通することでもある。
一方、大手外食チェーンでは独自の文化が構築されており、社内システムとの連携がないと運用が回らないなどの固有要件が多く、完全なフィットを目指すのであれば、カスタマイズが避けて通れないのが実情である。「企業がシステムに合わせるのか」それとも「システムが企業に合わせるのか」という議論は昔からあるが、そこに明確な優劣はない。が、その企業や店舗が築いてきた文化というものは尊重していくべきものではあると思う。


モバイルオーダーの今
モバイルオーダーとはスマホやタブレットなどから注文・決済をして、店頭で商品が受け取れるシステムであるが、店外・店内によって大きく機能が変わってくる。「店外」は店外からの注文をメインとなるが、テイクアウトやデリバリーが主となる。テイクアウトであれば注文後に指定された時間に店舗へ受け取りに行く形となり、デリバリーであれば登録された住所にライダーが商品を運んできてくれる。
Uber Eatsや出前館、Woltなどのデリバリーメディアからの注文一元管理機能に特化したサービスもある。店舗では複数のデリバリーメディアを利用することが多いが、各社ごとに専用のタブレット端末が支給されるため、注文管理が煩雑となって商品の準備が漏れてライダーとトラブルになることもある。そのため、混雑時の店内でいかにオペレーションを回せるのかを考慮した機能が多い。
また最近では、UberDirectのようにライダーだけを提供するサービスも増えている。マネジメントやコスト上のネックとなるライダーだけをかりて、自社でデリバリーを実現できるわけである。
「店内」は店中からの注文がメインとなるが、世間一般で「モバイルオーダー」と呼ぶものはこちらを指すことが多い。店内に設置された2次元コードから自身のスマホで注文画面にアクセスして利用し、注文はPOS端末と連携されてそのまま会計できるのが一般的である。
外食企業ではLINE公式アカウントをCRMに活用するケースが多く、モバイルオーダーをLINEミニアプリ化することで、注文時に「お友達」を増やしていく形にする店舗も増えている。店外と比べると、システムとして求められる技術要件は高いといえる。
店内では営業中の注文が入り続けるため注文件数が圧倒的に多く、特に食べ放題店舗で繁忙時間帯に桁違いの量となる。しかもスタッフがハンディ端末から注文したものも共有したり、POSとの商品やクーポン、会計などの各種情報をAPIで連携したりしなくてはならない。
ほかにも店内でモバイルオーダーがPOS端末と同一ネットワーク内で動かす必要があり、想定外のことも起きる。広い店舗では回線が弱かったり、無料Wi-Fiと共有されていて不安定になったりと、ネットワークの整備も必要となることが少なくないが、複数ベンダーが絡んでいることで、どの会社がどこまで何を調整していくのかの線引きは曖昧になりがちである。
モバイルオーダーの肝となるものとは?
モバイルオーダーでは、店内と店外ともに共通で「注文画面」「注文管理」「商品/オプション設定」「分析」「CRM」が肝となってくる。まず顧客が利用する注文画面を分かりやすく使いやすくすることが重要である。単価アップのためのおすすめ表示やオプションの見せ方などを工夫し、同じメニューを注文するケースも多いため再注文をやりやすくするなど、UI/UXのブラッシュアップがひたすら繰り返されている。注文管理は、店舗が忙しい中でもミスなくオペレーションできることを追求している。スタッフごとに表示する商品を分け、キッチンモニターやプリンター印字など、各社によって機能差がある。
商品/オプション設定は、登録や在庫管理などの運用をどれだけ簡易にできるのかが重要だ。POSとの商品を連携させなくてはならないが、POS端末もメーカーや種類によって仕様が異なるため、モバイルオーダーとしてどのように処理をするのかは重要となってくる。
分析とCRMについては、各ベンダーが力を入れている領域となる。店舗の状態をどのように見える化するのか、再来訪・再購買を促していくために誰にどんなメッセージを配信していくのかが重要となる。このあたりも、ベンダーによる機能差は大きいところとなる。
店舗のオペレーションは混雑状況で使用されるため、予想外のことが起きることが少なくない。机上の空論で設計しても実際の店舗では使えないみたいなことが平気で起きるが、これは飲食DX全般に共通することでもある。
モバイルオーダーの分かれ道
「外食DX」という言葉があるように外食業界のDX化は進んでおり、それに伴って関連ベンダーは次々に増えている。だが、各社の方針としてモバイルオーダーの「カスタマイズ導入をするのか」は分かれているといえる。感覚とはなるが、カスタマイズをしない会社が多いように思われる。それはSaaSとして構築したシステムをカスタマイズする工数や人材の確保であったり、モジュールやサーバーの管理や運用負荷などの課題によるものだったりすることが大きい。一方、大手外食チェーンでは独自の文化が構築されており、社内システムとの連携がないと運用が回らないなどの固有要件が多く、完全なフィットを目指すのであれば、カスタマイズが避けて通れないのが実情である。「企業がシステムに合わせるのか」それとも「システムが企業に合わせるのか」という議論は昔からあるが、そこに明確な優劣はない。が、その企業や店舗が築いてきた文化というものは尊重していくべきものではあると思う。
モバイルオーダーの第2フェーズに期待
モバイルオーダーはコロナ禍で本格的に普及をしたが、需要の高まりとともにベンダーが増えていき、明確な機能差も少しずつ埋まってきている。が、外部連携先は利害関係社によるしがらみや特許による制約などもあって、全てのモバイルオーダーが全く同じものとはならない。一方、ビジネスでは制約があるからこそ、その先の新しい発想が生まれるということもある。モバイルオーダーの第2フェーズが面白くなりそうである。(イデア・レコード・左川裕規)