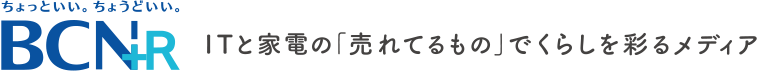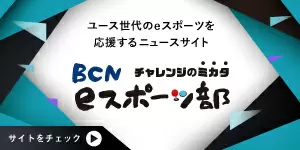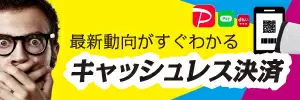テレビ市場で圧倒的存在感を放つTVS REGZA 全方位戦略が大当たりした理由をキーマンが語る(前編)
2025年1月20日、全国のパソコン販売店や家電量販店の1年間(2024年1~12月)のPOSデータを集計し、部門別に販売数量No.1のメーカーを表彰する「BCN AWARD 2025」の結果が発表された。テレビ部門は液晶テレビ(4K未満)部門、液晶テレビ(4K以上)部門、有機EL部門の3部門があり、液晶テレビの2部門を制したのはTVS REGZA。4K未満部門では4年連続4回目、4K以上部門では2年連続2回目の受賞となった。有機EL部門では昨年からワンランクアップの2位につけ、液晶テレビと有機ELを合算したテレビ全体でも3年連続トップを獲得。まさにテレビ市場において全方位で結果を残し、圧倒的な存在感を示した1年だった。強力な競合がひしめく市場において、なぜこれだけの成果を挙げることができたのか。今回は同社のキーマンである石橋泰博取締役副社長にインタビューし、好調の要因を探った。

石橋泰博取締役副社長
私のように東芝時代からレグザに関わってきている人間は非常に苦しい時期も経験しているので、「よくここまで来たな」というのが正直な感想です。
昨年の販売が好調だった要因として、シリーズ展開やモデル展開、サイズ展開が非常にうまく当たったという部分はあると思います。家電量販店の方とお話していても、「どのような要望のお客様がいらっしゃっても、必ずニーズを満たす製品がある」とおっしゃっていただけています。
昔に比べると、開発においても営業においても企業としての体力がだいぶつきました。そのおかげでバリエーションを豊富に揃え、全方位でお客様に刺さる製品を用意することができるようになりました。これは非常に大きかったです。
われわれは18年からハイセンスグループとして事業を展開していますが、「同グループのサプライチェーンを含むグローバルなスケール」と「日本市場にフォーカス(=ローカライズ)した製品開発」がうまくマッチし、1+1=3のような相乗効果が得られたのではないかと考えています。
――有機EL市場では23年の3位から24年で2位とワンランクアップしたものの、あと一歩というところでした。
今年こそはなんとかしたいと考えています。液晶テレビの新技術である Mini LEDの品質が上がり、有機EL市場全体のパイがなかなか広がらないという状況はありますが、「Mini LEDも本気、有機ELも本気」という当社のツートップ戦略に変わりはありません。
Mini LEDにはMini LEDの、有機ELには有機ELの良さがあります。お客様のニーズにはばらつきがあるので、レグザとして両方をしっかり向いた製品開発に取り組んでいきたいです。せっかくここまで体力がついて、しかも両方を追える立場にあるわけですから、その優位性を手放すつもりはありません。
どんなお客様にも合う幅広いラインアップを用意するという現在の体制は昔からやりたいと考えていたことでした。以前はそれをやるだけの基礎体力がありませんでしたが、ここ数年でシェアや売上が上がり、開発投資のためのリソースを十分に確保できるようになってききました。
また、ハイセンスグループに移ってきたときは営業部隊もいませんでしたが、現在はそのあたりも拡充され、売る能力も上がってきました。開発と販売の双方で良い流れが出来上がってきています。
もっとも23年から24年にかけては、われわれとしてもプレミアムラインを強化しようという動きは他社同様に行ってきました。大型モデルはもちろん高付加価値モデルのラインアップもだいぶ厚みをもたせることができたので、販売数量だけでなく販売金額も上がっています。今後もこのラインはより充実させていくつもりです。
――ハイセンスグループであることは、コスト面でかなり有利なのでしょうか。
テレビはPCやスマホと違って、商品のローカライズのボリュームが非常に大きいカテゴリーです。そのため、グループ傘下に入ったときから、ローカルとグローバルの部分をどう組み合わせるのがよいのか、議論を重ねてきました。
私も1カ月に1度はハイセンス本社のある中国・青島まで足を運んでいましたが、テレビに対する思想や生産体制はかなり違いました。少しずつお互いに擦り合わせながら、もっとも売上高に寄与できる組み合わせを検討してきて、ようやく完成形に近づいてきたのではないかと考えています。市場は固定化されることはないので「完成」することはありませんが、お互いのギャップのようなものはだいぶ小さくなっています。
――先ほど営業体制が整い、売る力が伸びたというお話がありましたが、具体的に営業手法はどのように変わったのですか。
ハイセンスグループに移ったときに営業部隊がいなかったのは、東芝時代には開発と販売が別会社として分かれていたためです。ひとつの会社の中に開発と営業の両方の部隊がいるという体制はTVS REGZAになってからのものです。
かつて開発と営業の距離が遠かったのですが、現在は物理的にも同じビルの中で働いており、非常に近い状態にあります。「なんでこんなことをやっているのか」「この技術はこんな凄いところがある」といった会話が日々活発に交わされています。
商品のセールスポイントがテキストベースではなく肉声で直接しっかりと伝えられるので、営業の商品知識やアプローチの方法もレベルが格段に上がっていると感じています。
また、売れない言い訳ができなくなったことも大きいですね。これまでは「これがなかったから売れなかった」などの後付けの理由が出てきていましたが、コミュニケーションが密になるとそうしたエクスキューズには事前に対策が打たれます。開発と営業の間で適度な緊張関係が保てているのです。
分かりやすい変化としては、開発を担うエンジニアが家電量販店に自社製品がどのように売られているのか見に行くようになりました。逆に営業がR&Dに話を聞きに来るといったことも頻繁に起きています。「ワンチーム」という意識が浸透しており、レグザを売っていくという共通目標に向かって一致団結しています。

苦しい時期を経ながらも、社内と社外の体制が整えられ、着実な成果を生み出しているTVS REGZA。後編では、大きな成果を挙げているプロモーション戦略などにフォーカスし、レグザの現在地点と今後の目指す方向性を紐解いていく。

液晶テレビの2部門でトップシェア!全方位戦略で販売店と顧客の信頼を獲得
――24年のテレビ市場において、液晶テレビでは4K以上と4K未満の両部門で複数年にわたって販売数量のトップシェアを獲得されています。この結果をどのように受け止めていますか。私のように東芝時代からレグザに関わってきている人間は非常に苦しい時期も経験しているので、「よくここまで来たな」というのが正直な感想です。
昨年の販売が好調だった要因として、シリーズ展開やモデル展開、サイズ展開が非常にうまく当たったという部分はあると思います。家電量販店の方とお話していても、「どのような要望のお客様がいらっしゃっても、必ずニーズを満たす製品がある」とおっしゃっていただけています。
昔に比べると、開発においても営業においても企業としての体力がだいぶつきました。そのおかげでバリエーションを豊富に揃え、全方位でお客様に刺さる製品を用意することができるようになりました。これは非常に大きかったです。
われわれは18年からハイセンスグループとして事業を展開していますが、「同グループのサプライチェーンを含むグローバルなスケール」と「日本市場にフォーカス(=ローカライズ)した製品開発」がうまくマッチし、1+1=3のような相乗効果が得られたのではないかと考えています。
――有機EL市場では23年の3位から24年で2位とワンランクアップしたものの、あと一歩というところでした。
今年こそはなんとかしたいと考えています。液晶テレビの新技術である Mini LEDの品質が上がり、有機EL市場全体のパイがなかなか広がらないという状況はありますが、「Mini LEDも本気、有機ELも本気」という当社のツートップ戦略に変わりはありません。
Mini LEDにはMini LEDの、有機ELには有機ELの良さがあります。お客様のニーズにはばらつきがあるので、レグザとして両方をしっかり向いた製品開発に取り組んでいきたいです。せっかくここまで体力がついて、しかも両方を追える立場にあるわけですから、その優位性を手放すつもりはありません。
グローバルとローカライズ、開発と営業。あるべき姿が見えてきた
――市場全体を見渡すと、高付加価値や大画面の製品に注力する傾向にあるため、レグザのローエンドからハイエンドまで網羅的にカバーしようとする全方位戦略はだいぶ特殊に映ります。いつ頃から計画されていた戦略なのでしょうか。どんなお客様にも合う幅広いラインアップを用意するという現在の体制は昔からやりたいと考えていたことでした。以前はそれをやるだけの基礎体力がありませんでしたが、ここ数年でシェアや売上が上がり、開発投資のためのリソースを十分に確保できるようになってききました。
また、ハイセンスグループに移ってきたときは営業部隊もいませんでしたが、現在はそのあたりも拡充され、売る能力も上がってきました。開発と販売の双方で良い流れが出来上がってきています。
もっとも23年から24年にかけては、われわれとしてもプレミアムラインを強化しようという動きは他社同様に行ってきました。大型モデルはもちろん高付加価値モデルのラインアップもだいぶ厚みをもたせることができたので、販売数量だけでなく販売金額も上がっています。今後もこのラインはより充実させていくつもりです。
――ハイセンスグループであることは、コスト面でかなり有利なのでしょうか。
テレビはPCやスマホと違って、商品のローカライズのボリュームが非常に大きいカテゴリーです。そのため、グループ傘下に入ったときから、ローカルとグローバルの部分をどう組み合わせるのがよいのか、議論を重ねてきました。
私も1カ月に1度はハイセンス本社のある中国・青島まで足を運んでいましたが、テレビに対する思想や生産体制はかなり違いました。少しずつお互いに擦り合わせながら、もっとも売上高に寄与できる組み合わせを検討してきて、ようやく完成形に近づいてきたのではないかと考えています。市場は固定化されることはないので「完成」することはありませんが、お互いのギャップのようなものはだいぶ小さくなっています。
――先ほど営業体制が整い、売る力が伸びたというお話がありましたが、具体的に営業手法はどのように変わったのですか。
ハイセンスグループに移ったときに営業部隊がいなかったのは、東芝時代には開発と販売が別会社として分かれていたためです。ひとつの会社の中に開発と営業の両方の部隊がいるという体制はTVS REGZAになってからのものです。
かつて開発と営業の距離が遠かったのですが、現在は物理的にも同じビルの中で働いており、非常に近い状態にあります。「なんでこんなことをやっているのか」「この技術はこんな凄いところがある」といった会話が日々活発に交わされています。
商品のセールスポイントがテキストベースではなく肉声で直接しっかりと伝えられるので、営業の商品知識やアプローチの方法もレベルが格段に上がっていると感じています。
また、売れない言い訳ができなくなったことも大きいですね。これまでは「これがなかったから売れなかった」などの後付けの理由が出てきていましたが、コミュニケーションが密になるとそうしたエクスキューズには事前に対策が打たれます。開発と営業の間で適度な緊張関係が保てているのです。
分かりやすい変化としては、開発を担うエンジニアが家電量販店に自社製品がどのように売られているのか見に行くようになりました。逆に営業がR&Dに話を聞きに来るといったことも頻繁に起きています。「ワンチーム」という意識が浸透しており、レグザを売っていくという共通目標に向かって一致団結しています。

苦しい時期を経ながらも、社内と社外の体制が整えられ、着実な成果を生み出しているTVS REGZA。後編では、大きな成果を挙げているプロモーション戦略などにフォーカスし、レグザの現在地点と今後の目指す方向性を紐解いていく。