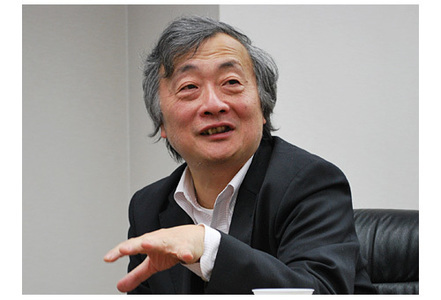オーディオビジュアルの世界で、その黎明期から独自の評論と提言で活躍している麻倉怜士さん。オーディオ再入門者のための『やっぱり楽しいオーディオ世界』(アスキー刊)など評判の著書も多数あり、この世界のトップランナーとしてずっと走り続けている。そんな麻倉さんに、かつて副編集長まで務めた雑誌『プレジデント』編集部時代のエピソードや、音と映像を取り巻く世界の変遷などを聞かせていただいた。【取材:2009年3月25日、BCN本社にて】
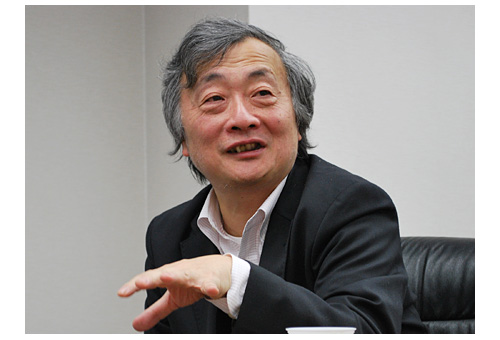
「とにかく書くのが生活。起床したらすぐに2、3行書いて、顔を洗ってまた書く。
そんな日常ですね」なのだそうだ
「千人回峰」は、比叡山の峰々を千日かけて歩き回り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借しました。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れることで悟りを開きたいと願い、この連載を始めました。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
株式会社BCN 社長 奥田喜久男
<1000分の第40回>
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。
奥田 麻倉さんとは、もう30年以上のおつき合いになりますか。
麻倉 まだ20代の頃でしたから、ずいぶん長いです。
奥田 麻倉さんが『プレジデント』誌の編集者だった時代ですね。
麻倉 奥田さんと最初にお会いしたのは、コピー機の市場調査の取材だったと記憶しています。1974年にプレジデントに入社しましたから、その翌年頃ですかね…。
狭き門の突破に役立った前職の経験
奥田 プレジデントの前は、日経新聞社に勤めておられた。麻倉 そうです。1973年に日経に入って、1年だけですが、大阪の工場にいました。記者ではなくて内勤で、実際の仕事はゲラを刷ってそれを見て修正する校閲・査閲ですね。
奥田 場所は大阪のどこにあったんです?
麻倉 当時は高麗橋です。駅でいえば、京阪電鉄の北浜の近くでした。毎朝7時に出社して、といっても寮が徒歩1分のところにありましたから、朝風呂に入って食堂でカレーライスを食べて出勤と、毎日そんな繰り返しで、まあ工場労働者でしたね。
奥田 現場だったんだ。
麻倉 そうです。それで1年間はしっかりとやったんですけど、まあ大阪という土地柄にも何となく合わない気がして、東京へと…。
当時、東京には土日に時々帰っていました。そんな時にちょうど新聞の求人欄に、プレジデントという会社が出ていて、青山にあって格好よさそうだなと思って入社試験を受けました。そしたら、3000人ほどの応募者の中で受かったんです。
奥田 へえ、それはすごい。
麻倉 実はこれが馬鹿みたいな話で、なんで受かったのかというと、前職が役に立ったんですね。ああいう入社試験には、知能テストのようなものがあります。たとえば、たくさん並べてある文章の中から間違いを見つけるというのがあります。そんなものは日経で校正を1年もやっていたわけですから、まったく楽勝で、目でパッパッとスキャンすれば、変な箇所が自然に浮かんでくるんです。まあ1年もやっていれば、知能テストのベテランになれるわけです。
奥田 なるほどね。
麻倉 そこで学んだ教訓は、どんな仕事でもしっかりやっておけば、どこかで役に立つということでした。そんなことでプレジデントに入社できたわけです。
逆転の発想で雑誌が大変身!
奥田 プレジデントへの入社が1974年ですか。新人訓練みたいなものは?麻倉 特に記者教育みたいなものはなく、いきなり現場に放り込まれて仕事を覚えたという感じでしたね。当時と今とはいろんな面で違うでしょうが…。まあ『プレジデント』も今まで3回くらいは大きな変革をしていると思いますね。今の『プレジデント』は中間管理職の出世マガジンみたいですけど、時代なんでしょうかね、ぼくらの頃はそんなのは下品でやっちゃいけないとされていた。
奥田 プレジデントが変わったとおっしゃいましたが、麻倉さんはどの時期に入社されたわけですか。
麻倉 第1期の終わり頃でしたね。ぼくが入った時は、『プレジデント』も『フォーチュン』の日本版という感じでして、まあ最初はそれでも外資の経営方式だから、斬新で結構成功するケースもあるんだけれど、だんだんそれが読者に飽きられてくると、本当に日本化しないといけないという時代に入ってくるんですね。ちょうどそのような過渡期にぼくは入社したんですよ。
奥田 第1期の『プレジデント』というのは。
麻倉 一応は成功したんですけど、後発の『日経ビジネス』にだんだん抜かれてくるんです。あちらは非常に実利的で戦略志向で、ビジネスマンにすぐ役立つような内容。それに比べると、当時の『プレジデント』は「高踏派指向」なんですよ。
奥田 高踏派指向って、どういうこと?
麻倉 たとえば、「いった」という表現を認めないんですよね。必ず「いつた」と書く。中の「つ」が小さくないんです。
要するに、これが自分のスタイルだというわけ。従来の日本語にない翻訳調みたいな感じを入れて、ちょっとおしゃれで他の雑誌とは違うぜというような。小さな「っ」がないと、流れていくような不思議な日本語なんだけど、ちょっと変わっているなという…。
編注:高踏派(高踏主義)とは、19世紀のフランスで興った「詩の文学様式」を指す。
奥田 それは何年頃まででしたか。
麻倉 最初、横組みだったんですね。『フォーチュン』の記事の翻訳が半分ぐらいあったから、そういうスタイルだったんでしょう。その頃は、他にそういうタイプの雑誌もなかったし。
奥田 おしゃれですね。
麻倉 確かにおしゃれで、日本の土着でなくて外国から入ってきたようなスマートな感じで…。ちょうどドラッカーとかがもてはやされた時期で、アメリカ的な経営の考えが尊ばれたという時代背景がありました。
ところがやっぱりね、こんなことをやっているとだんだんダメになってくるんですね。ぼくが74年に入って、76年頃が最悪で、社員一人100冊購読契約作戦なんかやらされたことがありましたね。編集部も総出で知人に売りまくれという。
奥田 そのあたりから第2期に入っていくんですね。
麻倉 そうです。これではもうダメだというんで、世界文化社で『家庭画報』を立ち上げた本多光夫さんが招かれた。本多さんはもう亡くなりましたけど、ご存じの方も多いと思いますが、諸井薫というペンネームで男の哀愁をいろいろと書いていた方です。
『TIME』の顧問だった彼が切り札として来たんです。ああいう人は面白いですね。すぐには何も言わない。半年ぐらいは、問題点は何か、できるやつは誰か、なんてじっと見ているんです。
奥田 ほう、なるほどね。
麻倉 それでいよいよ1977年に、『プレジデント』の紙面構成を横組みから縦組みに変えていくんです。そして80年からが飛躍期です。82年ごろからはさらにぐっと伸びて87年ごろには28万部まで到達しましたね。
奥田 それがいつごろまで続くの?
麻倉 バブル末期の1992~93年ごろまではこれが続きました。ピーク時には1号あたりの売り上げが広告を含めて10億円くらいあったんじゃないかな。それが12号ですから、いろいろ含めると年間150億円くらい稼いだと思いますよ。
奥田 なぜ、そんなにうまくいったのですかね。
麻倉 とにかく日本化したことですね。横組みはダメ、日本語は縦組みの文化だと。それから内容も翻訳ではダメで、日本のビジネスマンにニーズのある記事をわれわれで作らねばならないと、それからもう一つはスタッフライターから編集者へということですね。
奥田 スタッフライターから編集者へというのは?
麻倉 記者でなく、記事を制作するプロデューサーになれということですね。