前例や常識にとらわれない思考がイノベーションを生み出す――第116回(下)

アキュセラ 会長・社長兼CEO 窪田 良
構成・文/小林茂樹
撮影/津島隆雄
週刊BCN 2014年08月04日号 vol.1541掲載
窪田良さんは、小さい頃、勉強が得意でなかったという。後年、医学や製薬開発の世界で最先端を走る、知的でエネルギッシュな姿からは想像できない。しかし、自身の努力とある先生の支援によって、まるで生まれ変わったかのような変化が起こる。そして、慣れないアメリカでの生活を通じて、「何でも自分でやる」という自立心を身につけていった。私は著書にサインを求め、好きな言葉を添えてもらった。そこには“Never give up”とあった。(本紙主幹・奥田喜久男) 【取材:2014.5.28/東京・港区赤坂のオークウッドプレミア東京ミッドタウンにて】

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。
あきらめずに努力すれば突然、成長の瞬間がやってくる
奥田 上梓された本(『極めるひとほどあきっぽい』)によると、お父さまが外国航路の航海士で、子どもの頃、アメリカで生活されたそうですね。窪田 小学校4年生のとき、マンハッタンの対岸、ニュージャージー州のフォートリーという町に移り住みました。
奥田 初めは英語がまったく理解できず、成績も低迷していた窪田少年が、あるときを境に、一気にトップに躍り出たというエピソードがあるそうですね。
窪田 あれは貴重な経験でした。勉強ができない時代は、「こんなに嫌いな勉強をこれだけしたのに20点しか取れない。やっぱりダメだ」と思っていました。ところが、ニューヨークの補習校で出会った川端英子先生は、とても親身になって指導してくださった。そんなに愛情を注いでもらっているのだからと、必死に勉強しました。するとあるとき、12歳か13歳の頃、突如、クリティカルマス(臨界点)に到達したんです。成長はリニア(直線)ではなく、不連続で階段状にやってくるんですね。
その後は、クラスで1番を取り続けました。これは本当に不思議でした。人生が変わりましたね。アメリカに行って、英語ができるようになったのもある日突然で、小学4年生の終わり頃、それまで「雑音」にしか聞こえなかった英語が、急に意味をもつ「言葉」に変わりました。ここでも、クリティカルマスを経験していたのです。そんな時期に川端先生に出会って、語学だけでなく、努力すれば何でもできると思うようになったのです。努力は裏切らないものだということが骨身にしみて、やってやろうと思いました。
奥田 それが、窪田さんのいわばOSになったのですね。
窪田 そうですね。それがベースにありますね。いくら結果が出なくても、どこかで必ず結果が出ると思い込むことができる。だから、あきらめずにやり続けられるんです。ふつう大学院は4年で修了するのですが、私は緑内障の原因遺伝子ミオシリンを見つけるのに7年かかりました。大学院に7年通うというのは決してほめられることではありません。でも7年間あきらめなかったおかげで大発見できたわけです。多くの人は、4年であきらめるか、最初から4年で結果が出るようなテーマしか選びません。でも私はあきらめきれずに研究を続けて、ようやくみつけることができました。やり続けてよかったな、と。最初に小さな成功体験があったからこそ頑張ることができて、頑張ってうまくいったから、それがどんどん強化されて、より大きな課題に挑戦しようという気持ちにつながったのです。
異なる価値観の人々が共通の目標で共存できる世界
奥田 ところで、その恩師の川端先生はお元気なのですか。窪田 ええ、いまでもおつき合いさせていただいています。実は、最後の授業のとき、私たち生徒が20歳になる年の4月1日午後6時に、上野公園の西郷隆盛像の下で会いましょうと約束したんです。
奥田 そこで再会するまでに、コンタクトをとったのですか。
窪田 まったくとっていません。小学校を卒業して、大学2年の20歳まで一度も。どこにいらっしゃるかも知りませんでした。当時は、もちろんインターネットもありませんし、手紙を出すこともありませんでした。
奥田 実話ですか? 映画にしたいような話ですね。
窪田 このとき、朝日新聞に取材されて、地方版に掲載されたんです。もう一人の先生と半ば冗談で「何人来るかしら」といって私たちと約束を交わしたそうです。それで実際に来たのが、私を含めて3人でした。
奥田 それは感動的ですね。もしかしたら新薬をみつける以上に貴重なことかもしれない。
窪田 そうですね。一生大切にできる何にも代えがたい思い出であり、出会いだと思います。私は川端先生をはじめ多くの人に助けられ、恵まれてきたと思いますね。
奥田 新薬が完成した後、その先10年というのは、どんなことを考えていますか。
窪田 私の会社には、トルコ、イラン、イギリス、ウクライナ、ロシアなど、世界中からスタッフが参加してくれています。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、仏教、無神論者と宗教もバラバラ、サイエンスの世界にいても進化論をまったく信じていない人すらいます。これほどに価値観の違う人たちが、同じ屋根の下で、「世界から失明をなくす」という目的のために、お互いに協力し合いながら仕事をしています。スタッフの笑い声が聞こえると、いくら大変な思いをしていてもホッとします。生きていてよかったと思うんです。
このように価値観やバックグラウンドがまったく異なる人たちが、共通の目標のためには共存できるということを、モデル化できないか、お互いの違いは違いと認めて、地球上のコンフリクト、無用な殺し合いや摩擦を減らせないかということに興味をもっています。私が海外に住む日本人だからかもしれませんが、それをどうやって伝えていくかということにとても関心がありますね。
例えば、私たちが携わっている失明を治す飲み薬というのは、世界中の誰もが価値あるものと認めてくれると思います。それは、宗教や国家体制がどうあれ、基本的に変わらないものでしょう。そのような普遍的な目標をつくって、みんなで一緒にやるのも悪くない、いや、一緒にやらなければできないというかたちにできたらいいですね。キリスト教の人も、イスラム教の人も、ユダヤ教の人も、仏教の人もみんな必要だ、だから一緒にやろうよと。
奥田 その思いはどこから来ているのですか。
窪田 子どもの頃、当時はアメリカで日本に対するマイナスイメージを並べ立てられました。ショックでしたが、世界にはこんなに違う価値観の人がいるのかと実感し、どこかで共存できる方法がないかと感じたことが原体験としてあるからかもしれません。ただ、アメリカでつらい思いもしましたが、すごく世話にもなりました。だから、いまアメリカで仕事を続けていられるのだと思いますね。
奥田 日本のため、世界のため、ますますのご活躍を期待しています。
こぼれ話
少年の頃、アメリカに渡った。治安のあまりよくない地区に住居があった。「本当にいじめられましたね」と、話のなかにはゾッとするような危険なシーンもあった。英語がほとんど喋れない、落ちこぼれの日本人の子ども、10歳前後の頃だ。それでも頑張れた。「川端先生がいてくれたからです」。通っていた小学校には日本人の先生がいて、補講をしてくれた。それが川端先生だ。小学校を卒業するときに20歳での再会を約束した。「20歳の年には慶応病院に在籍していたので、信濃町から上野まで電車で行きました」。そして感動の再会。本当の話なのかと確認した。「実話です」と。自分が子どもの頃、壺井栄の『二十四の瞳』を読みながら涙したことを思い出した。窪田さんは眼科医だから、きっと目の清掃をしてくれたのだろう。新薬で多くの人を幸せにしてほしい。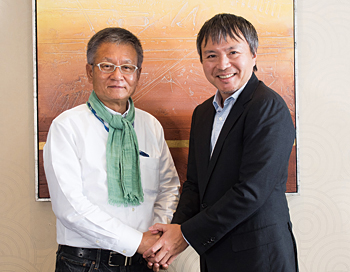
Profile
窪田 良
(くぼた りょう) 1966年生まれ、兵庫県出身。慶應義塾大学医学部卒。医学博士。研究過程で緑内障原因遺伝子であるミオシリンを発見し、「須田賞」を受賞。眼科専門医として、緑内障や白内障などの手術の執刀経験をもつ。その後、2000年に渡米。ワシントン大学で助教授として勤務。2001年に独自の細胞培養技術を発見する。2002年4月にシアトルの自宅地下室でアキュセラを設立した。現在、「飲み薬による失明の治療」を目指し、地図状萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性や緑内障などの眼科治療薬を開発している。全米アジア研究所(The National Bureau of Asian Research)の理事。慶應義塾大学医学部客員教授。2013年にはウォール・ストリート・ジャーナルが「世界を変える日本人」として紹介。著書に『極めるひとほどあきっぽい』(日経BP社)がある。






