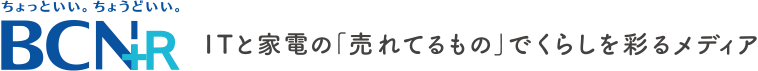人生最大の目標は電子立国日本の再生だ!――第324回(下)

大橋太郎
日刊電波新聞 電子ホビー入門アドバイザー 「日刊電波新聞」特任ライター
構成・文/小林茂樹
撮影/笠間 直
2022.12.22/東京都練馬区のご自宅にて
週刊BCN 2023年3月27日付 vol.1962掲載
【東京・練馬発】古希を越えた年頃ともなると、程度の差こそあれ、身体に不具合が生じてくる。今回の対談相手である大橋太郎は、両耳の難聴に苦しみ、補聴器なしでは日常生活に支障をきたす。現役のライターとして人と接し、またオーディオマニアでもある彼にとって耐えがたいことではないかと思ったが、よかったこともあるという。難聴になって初めてその不自由さがわかり、それがソリューションにつながるからだ。いまは耳の不自由な人とメーカーの技術者が共同開発した補聴器も使い、公私ともに聞こえのバリアフリーに挑戦しているという。へこんでばかりはいられない。
(創刊編集長・奥田喜久男)

『HAMライフ』の休刊をバネに
猛獣使いが新企画を繰り出す
奥田 1971年の春に二人とも電波新聞社の出版部に配属になったわけだけど、太郎は『ラジオの製作』とアマチュア無線雑誌の『HAMライフ』の両方に関わっていたんだよね。大橋 『HAMライフ』はCQ出版の『CQ Ham Radio』に対抗する形で出したもので、その創刊号は71年8月号だから、最初から二つの雑誌を兼務していたことになるね。モノづくりは好きだったし、回路図も読めて、無線やオーディオにも通じていたので、毎日の仕事は楽しかったな。
奥田 『HAMライフ』は、最終的にどうなったんだっけ?
大橋 創刊4年後に休刊になった。張り切りすぎちゃったんだよね。
奥田 そのいきさつを、もう少し詳しく教えて。
大橋 『HAMライフ』創刊の頃、皆川隆行という「トップ屋」、いわゆる週刊誌の目玉記事を書くやり手のライターのことだけど、その人が会社に来て、どうしても『HAMライフ』を手伝いたいといってロビーから動かないというんだ。それで、おまえが対応しろというので話を聞いてみると、ものすごい情熱で「アマチュア無線をもっと世の中に広めたい」と。
奥田 事件やスキャンダルがテーマではないのに、トップ屋が来るとは珍しいね。
大橋 ご自身が、アマチュア無線に夢中になっていたんだね。私にとっては、当時有名なトップ屋だったし、ジャーナリストとしても大先輩。私は皆川先生のとりこになって、くっついて歩くようになった。取材の作法をいろいろと教えてくれたし、新宿のゴールデン街にも連れて行ってもらった。吸っている缶ピー(たばこの缶入りピース)まで真似をするようになったんだ。
奥田 そんなに心酔していたんだ。
大橋 ところがあるとき、日本アマチュア無線連盟の土地買収に議論が起き、義憤にかられた皆川先生がそれを記事にした。役所で登記簿を見せてもらおうと粘り、ようやく「見るだけなら」と出してくれたその写しを私が素早く撮影して、それを『HAMライフ』に掲載したんだよ。
奥田 なかなかスリリングなシーンだね。
大橋 そうしたら、業界のほうから社長あてに「君のところにいる大橋太郎というとんでもない暴れ者は、無線業界にとって迷惑な存在だ」というクレームがついて、あえなく休刊ということになった。
奥田 会社員としては、きつい立場だなー。
大橋 それで『ラジオの製作』の編集部に戻ったんだけど、どうせならライバル誌の『初歩のラジオ』(誠文堂新光社)に勝ちたいと思い、皆川先生と一緒に、アマチュア無線より簡単で免許もいらないCB(市民無線)をはやらせようとした。その一方で、キングレコードのディレクターだった山田耕嗣という先生にBCL(海外の短波放送を受信する趣味)の連載を担当してもらった。幸いどちらの企画もヒットして、『ラジオの製作』の別冊として『BCLマニュアル』を出したら、これも10万部の大ヒット。これで『HAMライフ』の件で叱られた社長からもようやく認められた。
奥田 新しいブームを巻き起こすことで、名誉挽回できたんだね。
大橋 でも、皆川先生も山田先生もひと癖あるタイプで、いつも丁々発止のやり取りをしなければならない。だから「太郎は猛獣使いだ」といわれていたんだよ。
子どもたちに科学的リテラシーを
身につけさせてあげたい
奥田 紆余曲折はあったにしても、太郎の実力がいかんなく発揮されたんだね。大橋 その後、電波新聞社では『月刊マイコン』を創刊し、これが『ラジオの製作』を瞬く間に追い抜いてしまったんだ。そして、当時の「マイコン少年」が秋葉原などの電器店にたむろするようになり、上から少年向けのマイコン誌をつくれという話がおりてきた。でも『I/O』(工学社)や『月刊アスキー』(アスキー出版)、それに自社の『月刊マイコン』というライバル誌がある。簡単ではないと、いろいろテストを重ねていたんだ。
奥田 時代は、ラジオからマイコンに移ったと。
大橋 そんなとき、札幌でアマチュア無線ショップをしていた工藤裕司さんと知り合いになった。当時、北海道大学の学生にゲームをつくらせており、東京進出を狙っていて、その相談に乗ったんだ。
奥田 ハドソンの工藤兄弟だね。
大橋 そう。そのお兄さんのほう。ゲームのプログラムを入れたカセットテープの販路を探していたのだけど、それなら電波新聞社の支局網を通じて流通させればいいということになった。
それでこのとき、新雑誌には何を打ち出せばいいか聞いてみたところ「やはりゲームだ。ゲームの投稿を募ったらどうか」という。
奥田 その新雑誌が略称ベーマガ、『マイコンBASICマガジン』となるんだね。
大橋 そう。ベーマガには、前半に投稿されたゲームのプログラム、後半に最新のゲームの解析を掲載した。創刊4号目には10万部近く刷ったと思う。
奥田 いまでは考えられない部数だな。
大橋 ベーマガの編集と並行して、私はゲーム部門の責任者を命じられた。ハドソンとの取引が終わり、自前でソフトをつくれないかということで私に白羽の矢が立った。でも、編集の仕事で手いっぱいだった私はなかなか動けなかった。そんなとき、副社長の平山哲雄さん(後に社長、勉氏の父)が私の机の上に百円玉を積み上げて「ゲームセンターに行ってきてください」と。実は、副社長は、ナムコから『ゼビウス』などのアーケードゲームをマイコンに移植するためのライセンスを20タイトルも取得していたんだ。
奥田 それはずいぶん大胆な経営判断だね。
大橋 副社長は、アメリカでそうしたムーブメントが起きていることを知っていたんだね。
でも、ナムコからは資料もソースコードももらえなかった。だから、ソフト開発の人材をかき集める一方で、最終面までクリアできる日本一ゲームのうまい高校生を探し出して、プレイしているときにすべての面を撮影したんだ。最後までクリアできなければ、開発も何もできないからね。
奥田 ところで太郎はいろいろな仕事や趣味にのめり込んできた感じがするけど、何にひかれてそんなに夢中になれるのかな。
大橋 「えっ!」と驚き、「こんなことあるのか。知らなかった」という思いだね。実は50歳のとき、出版部から新聞に異動したんだ。雑誌のヒットメーカーで、会社にかなりの貢献をしてきたと自負していたのに、まったく仕事のやり方が異なるところに放り込まれたわけだ。でも、半導体、フラットディスプレイ、ハードディスクといったジャンルを担当することで視野が広がり勉強になったし、CESなどの展示会や内外のメーカーを取材することはとても面白く、夢中になることができた。
奥田 きっと、その好奇心と探究心が太郎の強みなんだろうね。それで、今後の目標は?
大橋 最大の目標は、電子立国日本の再生だね。子どもたちに幅広い科学的リテラシーを身につけてもらうため、いまでも手弁当でいろいろなイベントに顔を出している。でも、この発想は50年前の昔と変わらないんだよ。
奥田 まだまだ現役だね。ずっと元気で活躍してくれよ。
こぼれ話
伊勢の大学で学生時代を満喫して、就職先の東京に向かったその日のことはいまだに覚えている。ワクワクというか、緊張感も相まって周囲が目に入らないほどの躁状態であったように思う。1971年4月1日、電波新聞社の社員として社会人のスタートを切った。研修を受け、配属先で出会ったのが「大橋太郎」である。“ほ~”彼なんだ、彼が大橋太郎なんだ、と思った。私たち同期生は大学4年生の夏休みに東京と大阪の電波新聞で新聞販売の実習を受けた。まあ、インターンシップのようなものだ。太郎はその時、東京組の新聞販売実績で一番だった。私は大阪組で2番。どうやってもトップの座にはつけなかった。たかだか新聞の拡販部数の競い合いじゃないかというなかれ。商品を売るには何か、コツというか技術があると思った。また、その格差にも愕然とした。そんな思いを抱きながら、社会人生活が始まった。配属先は出版部だった。私の背中の後ろに太郎が座っている。彼はすでにアマチュア無線の世界で名が売れている。社会人1年生といっても、すでに得意の技をもっている。眩しい同期生だ。私は『電子と経営』という創刊雑誌に携わった。前の月までは伊勢神宮のある伊勢でお酒(お神酒)ばかりを飲んでいて、古事記や祝詞、祭式を学ぶという神職の環境の中にあった。それが突然、東京の新聞社で電子や経営という未知の分野の雑誌作り……。しかも東京の地理にうとい。わからないことだらけだったからだろうか、すべてが新鮮だった。夜になると、居酒屋の暖簾をくぐり、帰るのは深夜。寮の真っ暗な部屋にこっそり潜り込んで寝た。こうして綴りながらも、楽しい思い出ばかり。印刷所は凸版印刷だった。営業担当の方に雑誌作りのイロハを教わった。凸版の板橋工場に出向いての出張校正がまたまた楽しいことばかり。時には作家の方の顔もあり、終わりの見えない仕事も楽しくて、本作りを通して社会に一歩踏み出した感じだった。とにかく、仕事をし続けて、よく酒を飲んだ。
編集活動は面白い仕事だと思う半面、編集内容の大半を占め始めたコンピューターのことがチンプンカンプンだ。兎にも角にも専門用語がわからない、構造がわからない、業界の実態がわからない、企業名がわからない。それが3年を経過する頃からコンピューターも、雑誌作りも、業界も、何よりも夜の東京事情に明るくなり始めた。さらに少しずつ社会の話題が見え始めてきた。その後、独立して『BUSINESSコンピュータニュース(現・週刊BCN)』を創刊し、メディアの発行者として40年が過ぎた。
ふと周囲を見回すと、太郎が目の前にいることに気がついた。ある時、「一杯やろうよ」のひと言で50年の時間軸を取り戻した。今回のインタビューは自分史の振り返りでもあり、かつての大橋太郎に再会したドラマでもあった。そのことに深い巡り合わせを感じる。ありがとう。

心に響く人生の匠たち
「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。
「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。
※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。
Profile
大橋太郎
(おおはし たろう)
1948年12月、東京生まれ。自由学園高等部を経て、東海大学文学部広報学科卒業。71年4月、電波新聞社に入社。『ラジオの製作』編集長、『マイコンBASICマガジン』初代編集長などを歴任する。現在は、電子ホビー入門アドバイザー、「日刊電波新聞」特任ライター。子ども向けの電子工作・プログラミング教室を運営するKidsVentureなどの特別顧問も務める。